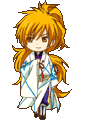真実に変えるための願い
2009.11.14
九郎生誕記念SSその7。
- 九郎×望美
宴を抜け、酔いを醒ますために庭へ出た九郎は、そこに先客が居た事に気付いて足を止めた。同時に相手も九郎に気付いて振り返る。
「あれ、九郎さん」
星空を見上げていた少女は、九郎を見て目を瞠る。
「どうしたんですか。主役が宴を抜けちゃ駄目でしょ?」
小走りに近づいてくる彼女へ、九郎は緩く笑みを向けた。
「少し酔いを醒まそうと思っただけだ。……だが、よかった」
「何がですか?」
「お前を探さないとな、と思っていたんだ」
訝しげに首をひねる少女へ「少し歩かないか」と声をかけ、手を差し伸べる。
躊躇うことなく重ねられた手のひらを握り締め、足元に気をつけろよ――と気遣う言葉を口にしてから、九郎はゆっくりと歩き出した。
庭を彩るはずの花々は闇に隠れているが、秋の花の香りが其処此処に満ちている。どこを目指すと言うこともなく足を進めれば、その爪先はいつも二人が剣の稽古をする広場の方へと向かっていく。習い性のようなものだな、と苦笑すれば、私たちらしいじゃないですかという応えが返り、二人揃って小さく笑い声をあげた。
「ところで、なんで私を探そうと思ってたんですか?」
「ああ。お前にちゃんと、今日の礼を言いたかったんだ。本当にありがとう、望美」
「やだなー。改まって言われると恥ずかしいですねぇ」
満月に近い月明かりの元では、互いの表情もよく見える。望美の目元に浮かぶのは、淡い照れの色彩。
「私一人じゃ何も出来なくて、皆が手伝ってくれたから出来たお祝いですよ。それに本当は、この大変な時に騒ぐとは何事だ、とか言われたらどうしよう~とか、色々悩んだんです」
「……そうだな。確かにそう思う」
「うあぁ、やっぱり~」
「でもな」
がっくりと肩を落とす少女の手を、九郎は強く握り締めた。それは続きを聞いてくれ、と希うような仕草で、望美は慨嘆を止めて、九郎の横顔を見上げた。
「生まれた日を祝うというのは初めてだったが、存外嬉しいものだな。多分――いや、違うな。俺が嬉しいのは、望美、他でもないお前が祝ってくれたからだ」
言葉と同時に足を止めた九郎は、一歩遅れて立ち止まった望美の腕を引き、腕の中へと抱きよせた。
「んもう、急に引っ張らないで下さいよ!」
「すまん」
九郎は短く謝罪を口にしつつも、更に少女の身体を胸元へと引き寄せる。
酔っている。
その自覚は十分にある。だけど、その酔いは、酒だけではなく、今抱きしめる少女から齎される酩酊の様な想いの方がずっと強いのだ。
「――逃げないのか?」
「え?」
問いかけに返される声は、心底不可解に思っているような響き。
「その、こういうことをされて、嫌ではないのか?」
「知らない人なら叩きのめしますけど、九郎さんは許嫁ってことになってるし、いいんじゃないかなと」
ヒノエくんや弁慶さんで、大分慣れた気もしますしねぇ、という微妙に論点のずれている返答に苦笑しつつ、指にかかる紫苑の髪を梳けば、仄かに甘い香りが漂った。
「花の香りだな」
「え?」
呟いた言葉が聞こえなかったのか、望美が胸元で顔を上げる。
「なんですか?」
「いや。お前は良い香りがするなと言っただけだ」
少しだけ言い換えて告げると、腕の中の少女はぴたりと硬直した。
「く、九郎さん――酔ってる!? まるでヒノエくんみたいなこと言ってるよ!」
「お前、その『ヒノエみたい』っていうのは、一体どういう喩えだ」
眉を寄せた九郎は、短く息を吐き出した。
小首を傾げた少女は、言葉を選びつつ口を開く。
「なんか、口説きっぽい感じ」
「そりゃあそうだろう。……文字通り、口説こうと思っているんだからな」
九郎は髪を梳いていた手を離し、望美の片頬をそっと包み込んだ。無駄に口をぱくぱくさせている望美の顔を掬い上げると、夜目でも明らかなほど彼女の頬は紅色に染まっていた。
戦場で見るのとは異なる、どこか頼りなささえ感じる姿に、九郎はひた隠していた願いを口にする。
「望美。もし叶うならば――お前に触れる赦しが、欲しい」
春の神泉苑で告げた『許婚』と言う言葉。
何度も否定してきたけれど、本当はいつだってそれを真実にしてしまいたかった。
「お前が、好きだ。院への言い訳ではなく、本当の許婚であったらと」
真摯な思いだけを彼女の前へと差し出せば、今まで抱えていた躊躇いも惑いも全て溶け去ったかのように言葉が溢れてきた。
「お前を俺だけのものにする資格があればいいと、共に過ごす間、いつしか願うようになっていた」
初めて戦場に立った日ですら、これほどに緊張はしなかったと思う。
まっすぐに見返してくる翡翠色の輝きの中に写るのは、源氏の大将ではなく、ただの男となった自分の姿。
たった一人の少女に振り回される自分は、傍から見れば滑稽極まりないだろう。だが、どんな嘲りがあろうとも、本当に手に入れたいと願ったひと、彼女にさえ真実が届けば、それでいい。
「――くちづけても、構わないか?」
「駄目って言って、止めてくれるんですか?」
逆に問われた声に、九郎はぐっと息を飲んだ。
「お前が本当に、それを望むのなら」
低い声で応じれば、照れたような気配と共に、ゆっくりと望美の瞼が閉ざされる。震える睫に誘われるように眦へ触れると、淡く色づいた笑い声が望美の唇から零れ落ちた。かわいい、とか聞こえたような気がするが、空耳だと無理やり信じ込む。
(寧ろ、可愛らしいのはお前の方だ)
そっと内心で呟き、九郎は一人で照れる。その様子には気付かないまま、望美はやんわりと彼の背へ手を回してきた。着物の背を掴む細い指の感触に、九郎は目の眩むような幸福を感じ取る。
「駄目なんて、言うわけないです。私が言うわけないじゃないですか。九郎さんだから、言わないんです。九郎さんだから……」
頑是無い子供のように繰り返される望美の声は、暫く意味のない事を繰り返した後、最後の最後に『好き』という囁きへと収束する。
木々のざわめきにすらかき消されてしまいそうな響きだったが、九郎はしっかりと聞き取り、ゆるりと笑みを浮かべた。
「先の事は分からない。だけど――ずっと共にいて欲しい」
祈るような思いで告げ、九郎は柔らかな唇へ己のそれを重ね合わせた。
- END -
||| あとがき |||
御曹司生誕記念最後のお話は、九郎×望美です。
なんとかラブっぽい話に戻って来ました。というか、一応全部の話が、少しずつ繋がっている…はず、です。気分的には、長いラブストーリーを書いたような感じです。