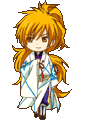優しい言葉
2010.11.09 祝・九郎生誕日
迷宮ED後、京へ戻ってきた二人…と仮定した微妙な捏造話
- 九郎×望美
「望美、いるか?」
声をかけると同時に、室の入口に掛かる御簾を潜り抜ける。
普通の乙女相手であれば非礼この上ない行動だが、この御簾の先にちゃんと目隠しの几帳が置かれている事を九郎は知っているし、この室に起居する張本人――つまり望美が、面倒なやり取りを嫌っているのが、一番の大きな理由だ。
「外から声かけて、入っていいですよ~って答えて、そこから更に二つも扉っぽいのを乗り越えてくるとか、すっごく面倒だと思いません?」
九郎は何度と無く、望美にそう問いかけられた事がある。
「いや、別に俺はそうは思わんが」
確かに、迷宮の事件で暫く過ごした鎌倉――九郎の兄が住まう場所ではなく、望美や将臣、譲が生まれ育った方の『鎌倉』と比べれば不便なのかもしれない。あちらでは来訪の挨拶は玄関チャイム一つで済むし、わざわざ扉を開けずとも『いんたぁほん』なる物で、壁越しに不自由なく会話が出来る。
だが、ここはその『鎌倉』ではない。
「いい加減、お前も慣れたらどうだ」
諭すように問いかければ、望美は九郎を真っ直ぐに見上げて頬を膨らませた。
「えーっ、だってそうしたら、私が九郎さんの所に行った時に、同じ事をしなきゃいけないじゃないですか」
「……分かった。要するに自分が面倒なだけなんだな?」
呆れ顔で確認すると、望美は満面の笑みで頷いたものだった。
そのような訳で、望美の我侭に押し切られる形で、九郎も訪問の礼を端折ることにしていた。
無論、立ち入るのはここまでだ。几帳の手前で足を止めると、もう一度名を呼ぶより早く、几帳の脇からひょっこりと望美が顔を出した。
「あれ、九郎さん、早かったですね」
「そうか?」
「もう少し遅いかと思っていました。ごめんなさい、まだ準備が終わってないんです」
望美の返事に、九郎は内心でなるほど、と首肯した。
なんとなく不自由そうな姿勢で首だけを出しているのは、首から下――つまりは衣の身支度が途中なのだろう。今更、望美の単姿を見たところでどうこう思う事は無いが、それを言うのは野暮と言うものだ。
九郎は笑って、鷹揚に頷いて見せた。
「構わん。庭でも見ながら待っている」
「え、そこで待っていてもいいですよ?」
ここに置かれている几帳は普通の物よりも丈が高く、九郎の背でも、上から奥を覗く事は出来ない。それでも身支度をする場の近くに男が居ては気分も良くないだろう――と、九郎は首を横に振る。
「いや、いい。外に出ているから終わったら呼べ」
「呼ぶの面倒なのに……」
「人を待たせるんだ、それくらいの手間はかけろ」
苦笑を噛み殺して告げてから、九郎は踵を返した。
入ってきた御簾を再び潜り抜け、庭に面した廂へ腰を降ろす。
美しく整えられた庭も、夏とは違い、大分淋しげな色合いとなっている。わびさびを解するものならば、こういった色合いもまた風流、と一句詠んだりするのだろうが、生憎九郎はそういった心得が無い。花は鮮やかに咲く方が綺麗だと思うし、葉も枯れた木々よりも、鮮やかに緑葉を茂らせる方が美しいと思う。
(ああ、でも紅葉は別か)
落葉する前に葉の色が変わる現象を、昔から不思議なものだと思っていた。
黄色は、どちらかといえば枯れた色に見えるが、紅色へと変わる葉はどうだ。元の緑に比べ、より一層鮮やかなものへと変化しているように見えるではないか。
京で源氏の大将として忙しなく過ごしている間は、正直そんな事を考える余裕すらなかった。日々を生き、戦い抜き、そして兄・頼朝の名代として、彼の名に恥じぬ働きをする事だけで精一杯だった。
少しずつ、己の為の時間として、色々な事を考えるようになったのは、あの『鎌倉』に行ってからだった。
迷宮の謎に息詰まった時、気分転換と称して、幾つか興味のあった事を調べたりもした。それは自分たちが「似ている」と言われた源平の物語であったり、この時代で生きる為に必要な基礎知識であったり様々ではあったが、そんな調べものの一つに、実は紅葉の仕組みもあった。
使われる用語が複雑すぎて、今ひとつどころか、全く理解出来なかったが、それでも一つだけ、九郎が分かった事がある。
それは、現象の理由など分からなくても、綺麗な物は綺麗だという事。
理解が出来なかったからこそ、素直にその美しさを受け止める事が出来るのだろう。
(……なんだ、俺も随分と感傷的になったものだな)
己の考えに、ふと苦笑を漏らしかけた時、かすかな衣擦れの音が九郎の耳に届いた。立ち上がって振り返るのと、白い指先が御簾を内側から巻き上げるのは同時だった。
「ごめんなさい、九郎さん。お待たせしちゃって」
ようやく一人で着付けられるようになった衣を纏い、望美が御簾を潜り抜けてくる。
「構わんと言っただろう。それにお前を待っている時間も、案外楽しかった」
「……どういう事です?」
訝しげな視線で見上げる望美の手を取り、九郎はゆっくりと階を降りた。そこに置いてあった沓を履き、庭を歩き始める。
「鎌倉に居た時の事を思い出していたんだ」
「あっちの、ですか?」
軽く瞬いた後の問いかけに、九郎は小さく頷き返す。
「といっても、別に大したことではないんだがな。……懐かしいか?」
「そりゃあ、勿論ですよ」
間髪置かずに答えた望美は、それでは言葉が足りないと思ったのか、考えるように小首を傾げつつ、言葉を継いだ。
「生まれ育った場所が懐かしいのは当然です。でも、戻りたいかとか聞かれたら、それはまた話が別ですからね」
望美の口調の意外なまでの強さに、九郎は瞬き、その真意を問う為に口を開いた。
「話が別とは、何故だ?」
「えっ、どうしてそんな事聞くかなぁ。別に決まっているじゃないですか。だって、戻りたいとか、そんな事を考えるくらいなら、わざわざ改めてこっちの時空に来たりしません。そんな甘い考えで、生きる場所を選んだりしませんよ」
当然じゃないですか、と望美は胸を張る。
その潔い表情に、九郎は思わず一瞬目を奪われる。
(そうだ)
心の奥から湧き上がる笑いを堪えながら、九郎は胸の裡で噛み締める。
(これが望美だった)
いつだって真っ直ぐに前を見つめ、幾度も迷い、悩みぬいたとしても、最後は自分の足で立ち上がり大地を踏み締める。自分はそんな彼女の手を取り、共に歩める事をどれだけ誇りに思ったことか。
「九郎さん、何がおかしいんですか? 私、そんな笑うような事、言いました?」
脇から袖を引かれ、九郎ははっと隣を歩く少女を見下ろす。
「いやこれは、決して可笑しい訳ではなく」
「違いません~! 普通笑うのは、おかしい時じゃないですか。……あっ、分かった、私の着物、どこか変なんですね!? すぐに着替えて……」
ぱっと踵を返そうとした望美を、九郎は大急ぎで抱き止める。
「ち、違う! そうじゃない!」
勢いよく腕を引き寄せた弾みで、ふわりと望美の足が宙に浮く。九郎は慌てて望美の腰を抱き寄せ、そのまま両の腕に抱き上げた。
「頼むから、落ち着いて話を聞いてくれ」
腕の中で凍りついたように硬直した望美の顔を覗き込み、九郎は低く嘆息する。
「落ち着けって言っても……」
無理、という呟きが聞こえたような気がするが、黙殺して九郎は言葉を続ける。
「いいか。普通は楽しいときや、嬉しいときも笑うだろう」
「それは確かにそうですが」
「じゃあ何故、可笑しいときだと決め付けた」
「それは――」
間近で覗き込む九郎の視線から目を逸らしつつ、望美はぼそぼそと口を開く。手持ち無沙汰なのか、白い指先がぎゅっと九郎の衣の胸元を掴む。それは恋人に甘えるというよりは、幼子が年長者に縋るような風に見えて、どこか頼りなげな雰囲気を感じさせる。
「何か変な事を言ったかな、とか。自分で恥ずかしく思っちゃったから……ですか?」
語尾を上げて疑問系で問う声に、深々と九郎は息を吐く。
「何故、俺に聞く。全く……あの言葉の、どこが変だと言うんだ。俺は嬉しかったというのに」
「えっ、ドコがですか!?」
「どこって、全部だ」
きっぱりと断定する言葉に、ぽかんと翡翠色の瞳が見開かれた。
「迷宮の謎を解いた後、お前と共に生きるならばどの時空でも構わんと、俺はそういう風に言ったな。だが結局お前は、生まれ育った鎌倉を去り、俺と共に京へ戻る事を選んでくれた」
噛み締めるように九郎が語る声を、望美は黙って聞いている。だが、無言の内に、九郎の衣を握る指先に力が篭る。
「俺は不器用な男だから、お前の時代で生きる事になった場合、そこへ馴染むのに酷く時間がかかっただろう。いや、努力を怠るわけではないが……例えば景時やヒノエのようには行かなかっただろう。だが、ここでは――」
九郎は一旦言葉を切り、苦笑とも自嘲とも見える複雑な色合いの笑みを口許に浮かべた。
「それなりに職務も地位もあるから、な。お前を不自由させる事は無いだろう」
「鎌倉の名代として、京の治安を守っている大将様が『それなりの職務』なんていったら、他のお仕事している人に怒られますよ」
「望美の前でしか言わないから、構わん」
「そ、う……デスか」
妙な具合に言葉を区切って応じる望美の頬は、うっすらと熱を含んで赤く染まっている。だが九郎はそれに気付かず、淡々と言葉を継ぐ。
「ああ、話がずれたな。それでだな」
「その前にですね、九郎さん」
「なんだ」
改めて続けようとした話の腰を折られ、九郎はやや不機嫌に応じる。
「いい加減、降ろしてもらえませんか?」
最前から抱き上げられたまま――いわゆるお姫様抱っこだ――なので、とにかく居心地が悪い。いや、寧ろ九郎に近すぎて、高鳴り続ける心臓に悪いと言うべきだろうか。
とにかく勇気を出して告げた筈の一言だったが、あっさりと九郎に切り捨てられた。
「断る」
あまりにも短く端的な返答に、言葉を失って見返した後、ようやく震える声を絞り出す。
「ちょ、なんでそこでお断りですか!」
「放したら逃げていきそうだからな」
だからだ、と笑う顔は、いつもよりも稚気に満ちていて、その一方で意地悪いようなものも含んでいる。
「逃げませんよ」
「どうだかな」
「逃げませんってば。ずっとずっと、九郎さんの傍にいるって決めたんですから」
両手で九郎の胸元に縋り、衣を強く握り締める。うっかり力を込めすぎて、滑らかな手触りの衣装、多分上質な絹なのだろうが、それに酷く皺が寄ってしまって慌ててしまう。だが今更手を放すのも変な気がしたので、そのままぎゅっと指の力を解かずにいたら、頭上から笑みを零す気配が落ちてきた。
「そうだな。俺も、お前が望む限り傍に――いや、違うな。俺が、お前に傍に居て欲しいんだ。そして、お前にも俺が共に在る事を望んで欲しい」
耳元で紡がれる真摯な声に、望美はくすぐったげに小さく身を竦めた。
「勿論ですよ。信じてくれないなら、毎日だって言いますから、安心して下さい」
「何をだ?」
訝しげに問い返す九郎の頬へ、背伸びするように首を伸ばして口付ける。
「大好き。愛してますよ、九郎さん」
眩しいほどの笑顔で、望美は笑う。
その表情に、九郎は先程追想していた事を思い出す。
理由など分からなくても、綺麗な物は綺麗だと素直に思う事が出来る。だが、理由があれば、尚更――それは愛しく、胸の奥を締め付ける。
彼女の紡ぐ優しい言葉は、九郎の心をただひたすらに幸せで満たす。
外見だけではなく、心そのものが美しい人なのだと思う瞬間だ。
「俺もだ」
愛してる、とは口に出して言えないけれど、万感の思いを込めて応じると、ゆっくり少女の唇へ己のそれを重ね合わせた。
- END -
||| あとがき |||
九郎さん、お誕生日おめでとうございます!!
というわけで、本当にギリギリ進行過ぎて(本当は昨晩の内に書き終えるつもりが、ちょっと体調不良で…寝てたら終わらなかった…)、でもなんとか9日の内にUP出来て(23時50分くらいだったけど!)ほっとしています。
アンケートで聞いた「迷宮ED後、京に帰った話」ですが、なんかあまり京EDじゃなくてもよくね? という内容すぎて…いつかリベンジしたいです。頼朝様とか出したりして…!(自分でハードルあげてどうする…)
そ、そんなわけで、こんな感じの話になりました。
本当は拍手お礼も九郎誕にあわせて、くのぞに入れ替えたかったんですが…ちょっと無理でした。もしも楽しみにしてくださった方がいらしたらごめんなさい。