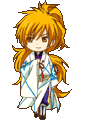その手が護るもの
2010.09.06
なにかの戦場にでる前の二人
- 九郎×望美
森閑と静まり返った野営地の夜。
明日は夜明け前に陣を出て、一斉攻撃をかける。朝日が昇る前に行動を開始するのだから、起きるべき時間は更に早い。
満月に程近い月は、既に中天を大きく越えていた。夜明けまでに残された刻限は少ない。早く寝なければ、と思いながらも、ただ焦る時間だけが過ぎて行く。
眠る努力を諦めた望美は、与えられた陣幕をそっと抜け出した。肩越しに振り返って朔が起きる気配が無い事をしっかりと確認してから、枯れ草を避けて土を踏み、人気の無い方へ歩いて行く。
木々の合間を抜けて一際強く吹いた風が、望美の髪を大きく乱す。視界を覆うように舞い上がったそれを慌てて押さえた望美は、適当に手櫛で整えながらひっそりとぼやく。
「結わいた方が邪魔にならないかな……」
九郎さんのように、との言葉は内心に留め置く。彼の名を呟いてしまえば、瘧のように心の奥に積もる感情が暴発してしまいそうだった。
(ここで、変えなければ)
失った時間を思いながら、剣の柄を握り締めた。
かつて白龍から与えられた剣は、本当は人を斬るためのものではないはずだ。それは神子が、怨霊と戦うための力の一助として――厳密には身を守るための道具として与えられたものなのだろうが、それでも望美は、戦で剣を振るう事を迷いはしない。
(違う、迷ってはいけない)
ほんの僅かな逡巡が、選べる未来を狭めて行く。しかし即断すればいい訳でもない。無限連鎖に陥らないように、緻密に道を選ばねばならないのだ。
強く強く、まるで指が折れんばかりに柄を掴み続けていると、末端からびりびりと痺れるような痛みが忍び寄ってくる。しかし身体の痛みがなんだというのだ。喪失の苦しみや恐怖に比べれば、こんなものは大したことない。
制服のスカートのポケットには、九郎が書いた腰越状があった。この世にはまだ無い、だが二度と書かせてはいけない。そんな望美の決意を形にしたモノ。
時空を越えても、変わらずに彼女の元にある書状。そっとポケットの上から押さえれば、かさり、と指先が小さな音を奏でた。
そして、それとは異なるもう一つの微かな音が望美の耳に届く。大股に、規則正しく地を踏み締める足音は、まっすぐにこちらへ近づいて来ていた。誰だろうと思う暇もなく、涼やかに響く声が背に投げかけられた。
「望美、どうした、そんなところで」
「九郎さん」
振り向き見上げた先にあるのは、訝しげな九郎の顔。満月が落とす影が、うっすらと彼の輪郭を彩っている。
「明日の出立は早い。少しでも寝ておかねば、辛いのはお前自身だぞ」
「心配してくれるんですか?」
「当り前だろう」
思わず問い返すと、九郎は何事でもないように素直に首肯した。
「戦は男のものだ。女であるお前を連れ出す事が正しいのか。白龍の神子であるお前しか怨霊を封印出来ないと分かっていてもなお、迷ってしまう。――ああ、無論お前の腕を疑っている訳ではないぞ?」
急いで言い添えた九郎は、笑顔のままで言葉を継ぐ。
「平和な世界から来たと言い、戦いなど縁がないと言いながら、花断ちを修め、俺やリズ先生の厳しい指導にも喰らいついてくる。なによりも――」
ふと言葉を切った九郎は視線を落とす。強い意志を孕んだ瞳が、望美の手元に吸い寄せられていく。
「――なっ、お前、手をどうした!」
「え?」
視線を己の手へ向ければ、剣を掴む指先から血の気が失せ、白く凝っていた。
「あ、あれ?」
急いで手を離そうとするが、あまりにも強く握り締め過ぎていたせいか、指が思う様に動かない。
焦っていると、脇からすっと腕が伸びてきた。
「全く。何をしているんだ」
ぐいっと腕を掴まれて反射的に眉を顰めれば、慌てたように「すまん」と短い謝罪が落ちてきた。そしてゆっくりと一本ずつ指を掴まれ、剣から引き剥がされていく。
もう痛みは存在しない。ふわふわと、柔らかな感触だけが望美の白い指を浸して行く。
武骨で色気も素っ気もない癖に、必要とあらばどこまでも優しくなれる指先。
誰かの手を取り、導く事に慣れた――九郎の手。
二十歳が大人の入り口な自分たちとは違い、この時代の人々は十代半ばに成人となる。それなりにきっと『大人の付き合い』もして来たんだろうし、そもそも身分も実力も申し分なく、ついでに見た目もイイ男な九郎が女性に放っておかれるはずない、と分かってはいても、なんとなく面白くないのだ。
それが嫉妬だとか子供っぽい我侭だとか、そんなあたりに分類される事は分かっていたけど、理解したからって止められるものではない。
「随分と、慣れてるんですね」
将臣やヒノエあたりが聞いていたら、あっさり八つ当たりだと判じたに違いない台詞にも、九郎は生真面目に頷き返す。
「ああ、そうだな。初めて戦場に出た兵士が、初めて人を斬った後に……こういう風になりやすい」
だから見慣れているのかもしれないなと笑い、九郎は最後の指を取り除いた。ついでに剣も鞘に収めてやる。
「これでよし、と」
誰に言うともなく小声で言った九郎は、そのまま望美の手を両手で包みこんだ。
「九郎さん?」
「まだ指先が冷たいな。このまま放っておいては、血が通わなくなってしまうだろう」
そういって、ごしごしと望美の手を擦り始める。
温めて血行を良くしようとしているのだろうが、生憎九郎の手も望美の手も、柔らかさとは程遠い。
稽古で出来た肉刺や固くなった皮膚が擦れ合い、微妙な感触を生んでいく。
「や、すぐに戻ると思いますけ、ど……」
応じる望美の声が、じんわりと笑いで緩んでいく。もじもじと肩を蠢かせば、怪訝そうな瞳が望美を捉えた。
「どうした」
「それ、くすぐったくて」
とうとう声をあげて笑いながら、望美は空いている方の指先で目尻を拭いた。
「……あはは、ごめんなさい。折角やってくれたのに。でもね、もう大丈夫ですから」
「本当か?」
「こんな事で嘘は言いませんよ」
翡翠の瞳を煌めかせて応じた望美は、九郎に包まれたままの手を動かし、ぎゅっと彼の指を握り返した。
「ほらね?」
「ああ、そのようだな」
互いの指を絡めるような形で繋がれた手を見下ろし、九郎は緩く息を吐いた。溜息に似た仕草を見咎め、望美は思わず瞬く。言葉より雄弁に問いかける大きな瞳を見返した九郎は、短く苦笑を湛えた後、口を開いた。
「先刻の話に戻るのだが――女であるお前を戦場に連れ出す事が正しいのか、未だに答えが出ないのも事実だ。だが同時に、お前が俺の傍にいない戦場が、想像つかなくなってきているのも確かなのだ。まだお前と出会って、半年も経たぬというのに……不思議なものだな」
九郎の言葉を黙って聞いていた望美は、うろたえた様に視線を逸らした。
なんだ、これでは自分が九郎の傍にいる事が自然だと。共に在る事を認められているようではないか。
(出会い頭に怒鳴られた記憶も、まだ新しいってのに、不思議っていうよりおかしいよ)
俯き、何とはなしに己の靴先を見つめる。耳のあたりで激しく鼓動が鳴り響いていて痛い。
望美、と改まって名を呼ばれ、そろそろと顔を上げる。そこには湖水のように澄んだ瞳があって、更にあまりにも優しい視線が待っていたので、望美は反射的に再び顔を逸らし――途中で頬に添えられた掌に引きとめられる。
実は、九郎が望美に触れてくる事は案外多い。
とはいえ、それは鍛錬の時に剣の持ち方を直すためであったり、姿勢を糺すためだったりするもの。直接肌に触れる事は殆どなく、精々あっても『許婚のフリ』をする時だけだ。だからこんな二人きりの状態での触れ合いに、望美は余計に戸惑ってしまう。
「九郎さ……」
戸惑いがちに名を呼ぶ声に、九郎の声音が重なる。
「本当に不思議だな。怨霊を封印する神子など、俺は信じてはいなかった。朔殿が黒龍の神子だと知り、また景時の妹御だからと尊重してはいても、心のどこかで、たかが女に何が出来るのだと、そう思っていたんだ」
九郎の視線が、ふと自身の左腕に向く。望美も反射的にその見つめる先を追った。しなやかな筋肉の乗った肩口、着物に隠れて見えない場所にあるのは、余人の目には見えぬ宝玉だ。
「だがお前と出会い、己が八葉だと告げられ――『神の力』を確かにこの身で感じてきた。これは確かに怨霊を挫き、神子を守るための力なのだろう。だが、寧ろ俺は、守るべき存在であるお前に、俺達こそが守られているのではないかと思う時すらある」
「そんなことないですよ。私は、いつも皆に助けられてばかりで、何も出来ていない」
ゆるゆると首を振る望美を引き寄せるように、九郎の手は更に強く少女の頬を包み込んだ。
触れる手が熱い。
違う。九郎の体温以上に、己の頬そのものが熱を孕んでいるのだ。
その緋色に気づかない筈はないだろうに、九郎の表情は穏やかなままで、声色にも変化がない。真っ直ぐで、真摯で、そしてどこまでも涼やかだ。
「いや。お前の瞳が、言葉が、その時々に欲しい何かをくれる。まるで俺の迷いを断つように――俺の願いを、知っているかのように」
(たとえ無意識にだとしても、それでどれほど俺が救われているか、きっとお前は想像もつかないのだろうな)
零れ落ちそうなほど大きく見開かれた翡翠の瞳を見つめ、掠めるように眦に唇を寄せた。
言葉か、それとも行為でか。ぴたりと身動きを止めた少女を見下ろしつつ、九郎は滲みかかる苦笑を腹の奥底に閉じ込める。
「まぁそれは、俺の思い込みかもしれん。もしくは、俺の願望かもしれないな」
ようやく口づけの混乱から回復した望美が、生真面目に問いかける。
「願望って、九郎さんの願いは、源氏の勝利でしょ?」
「なんだ、本当にそれだけだと思っているのか?」
揶揄するような響きに、目を丸くして九郎を見上げる。
「え? 違うんですか? あんなに兄上大好き★ 源氏大好き~な九郎さんなのにっ」
嘘だっ、絶対嘘だ、そんなの九郎さんじゃない、と言い募る望美に、九郎は今度こそ苦笑を口の端に乗せた。
「お前、俺を一体なんだと思っているんだ……いや確かに間違ってはいない。だが、それだけでもないという事だ」
「――…何を言いたいのか分かりません」
ぷくりと頬を膨らます少女に、九郎は声を立てて笑う。
「そうだな、今は分からなくてもいいさ」
「じゃあ、いつか教えてくれますか?」
「さて、覚えていたらな」
「忘れません」
きっぱりと望美は言い切る。
それは何気なく応じた九郎が驚くほどの強さで、二人の間の空気を揺らす。
「九郎さんの言うことは、なにひとつだって忘れません」
「――そうか」
九郎は望美の頬に添えた手をずらし、彼女の柔らかな髪をそっと梳いた。さらさらとした感触が指に心地いい。
「ならば、この戦いが終わったら聞いてくれるか?」
希う声に、遠く鳥が啼く声が重なる。
夜明けまで、あと僅か。暁降ちの一時を過ぎれば、互いの身は戦陣にある。生き残った先、未来へと繋がる約束を紡ぎながら、九郎は柔らかな戦神子の身体を抱き寄せた。
- END -
||| あとがき |||
9月6日! 九郎さんの日!(嘘です違いますごめんなさい)
いつもとっっても(←強調)お世話になっているお友達のお誕生日に寄せて書きました。
相変わらず殺伐です。お祝いと言う前提条件をきらり軽やかに無視した(笑)内容です。でも九郎はこれ位の方が書きやすかったり…。
時期は特にこれ、とは定めていませんので、お好きな戦闘の前あたりで想像して下さい。まぁ半年も~とか書いちゃったから秋以降な気もしますが。