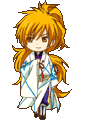心惑わす真珠
2010.05.04
[blog 10,000hitお礼SS]
- 九郎×望美
「九郎さんの馬鹿っ!」
そんな望美の叫び声が高々と響き渡った時、仲間たち――庭で洗濯物を干していた景時や、隣室で繕い物をしていた朔、もしくは弁慶の薬草整理を手伝っていた譲や白龍といった面々は、あぁいつもの事が始まったな、と思っただけだった。多分、怒鳴られた張本人である九郎も同様だろう。
だが、その叫びと同時に浮かんでいた表情を見たとき、九郎は激しく動揺した。
「なっ……の、望美!?」
「知らないっ!」
反射的に伸ばした手は、ぱしん、と小気味よい音を立てて跳ね除けられる。手に感じた痛みより、叩いた望美自身の方が傷ついた表情を浮かべていることより、なによりも、彼女の翡翠色の瞳を潤ませる涙の存在が、九郎の心を惑わせていた。
「なんでお前、泣いて……」
手を半端に伸ばしかけたみっともない格好のままで呟けば、はっと望美が己の眦に手をあてる。指先に感じる水滴に、ようやく涙の存在を自覚したのか、桃色の唇が、音も無くうそだ、と象るのが見えた。
濡れた指先を見下ろしつつ目を見開き――そして無言で踵を返した。呼び止める隙も無く、望美は御簾を乱暴に跳ね除けて走り去っていく。その膝元から一枚の布が零れ落ちたが、それを指摘する暇すら無い。
華奢な背を呆然と見送った九郎は、のろのろと手を下ろした。その途中で、無意識にきゅっと手を握り締める。届かなかった指先は、涙を拭うことすら許されなかった。ましてや、その涙の理由など思い至らない。
「いや、俺が悪いのだろうけれど」
何かの記憶に触発されて涙が出るという可能性も無きにしも非ずだが、思い出し笑いならともかく、思い出し泣き等聞いた事もない。つまり原因は間違いなく、直前まで対話していた九郎自身にあるはずだ。
ぽつりと零れた呟きの語尾を奪うように、鈴振るような声が重なってくる。
「全くです」
「朔殿」
滑らかな挙措で九郎の斜め前に膝をついた朔は、望美が置き去りにしていった布を、やや目を伏せるようにしながら丁寧に畳んで行く。黙って彼女の動きを眺めていた九郎が、途中で僅かに目を瞠るが、それは綺麗に無視して朔は自分の動きだけに集中する。やがて畳み終えた布を己の膝に載せると、改めて九郎に向かい直った。
「それで、何をあの子に言われたのですか?」
穏やかな笑顔で問う朔の瞳は笑っていない。静かな物腰で問い詰めに掛かる彼女の表情に気圧されるように、九郎は先刻の会話を思い出しながらしどろもどろな声を紡ぐ。
適宜相槌を打ちながら聞いていた朔は、ようよう語り終えて口を噤んだ九郎を見遣ると、ふぅ、と深々と息を吐いた。その仕草に全てが集約されている事を悟り、九郎は思わず視線を横に逸らしてしまう。それで再び朔に溜息をつかれ、ますます肩身が狭くなる。
「九郎殿のお考えに一々私が口を挟むのはおかしい事と存じてはおりますけれど、もう少しだけ、あの子の事も思いやって頂けませんか? どれだけ剣を修め、神子として戦陣に立っては居ても――まだ、子供なんです」
最後の一言だけを、言い悩むように僅かに言葉を切ってから告げた朔は、ようやく目元を和ませる。
「九郎殿だって、ずっと『源氏の大将』で居続けたら疲れてしまいますでしょう? 弁慶殿や、兄上とお酒を召している時など、全てが軍の話な訳でも無いと思っておりますよ。素のご自分に戻る時間も、ありますでしょう?」
「それは、確かに」
特に古くからの付き合いである弁慶の前ではそんな時もある、と思いながら九郎は頷く。
「そういう時間が、あの子にも必要なんです。――白龍の神子であること。白龍の神子を守る存在であること。その言葉に縛られすぎるのは良くないのではないかと私は思うんです。……怨霊の動きが激化している今だからこそ特に、心休める時間というのがあって然るべきではないのかしら」
そして、持っていた布を九郎に手渡してから朔は立ち上がる。
「八葉は神子を守る存在と言います。では、神子ではない望美は、八葉の方々――いえ、九郎殿に取っては不要な存在ですか?」
「まさか! そんな事は無い!」
迷うことなく断言した九郎へ、朔は優しい笑顔を向けた。
「そう思われるのでしたら、望美を探してきてやって頂けませんか? 今日ばかりは、私が迎えに行っても無意味でしょうから」
では失礼します、と言いおいて隣室へ朔は戻って行く。たおやかな後ろ姿を見送った九郎は、渡された布に視線を落とした後、ゆっくりと立ち上がった。
「望美、居るか?」
低く声をかければ、言葉は無くとも身じろぐ気配が伝わってくる。
御簾と几帳を越えた向こう側は、望美が眠る時に使っている一室である。少女の姿は目にする事が叶わないが、とりあえず居るのだ、という事が分かり、九郎はほっと息を吐いた。もしも邸の外に出られていたらどうしようかと思っていたのだが、流石にそこまで猪突猛進ではなかったらしい。
室の入り口にある柱に背を預けるようにして腰を降ろすと、九郎は「すまなかった」と口火を切った。
「朔殿にも怒られたたが、兎角俺はお前に対して配慮が足りなさ過ぎるようだ」
「……別に、謝る必要なんかないです」
何か布越しにでも喋っているかのようなくぐもった声が返ってくる。寝具でも頭から被っているのだろうか。九郎は見えないと分かりつつも、ゆるりと首を左右に振った。
「いや。お前の気持ちも考えずに酷い事を言った。その……入っても、構わないか?」
「駄目です」
ぴしゃりと、まるで門扉を閉めるような勢いで返ってきた言葉は、予想以上の痛みとなって九郎の呼吸を止めた。そこまで嫌われたのだろうか、と考えた瞬間、その言葉が含む甘さに九郎の息が再び止まる。
好き嫌いなど、そんな感情に惑わされたことなど今までなかったと言うのに、ふと浮かんだ言葉は、酷く九郎を狼狽させる。
内心で慌てふためいている九郎の耳に、小さな音が届いてきた。はっと振り返れば、片手に薄い衣を引きずりながら、望美が御簾を潜り抜けてくる所だった。ぺたぺたと、裸足の足音を響かせながらやって来た望美は、途中で衣を床に落とすと――意図的にではなく、手の力が抜けて落ちたような感じだったが、そのまま九郎の前を通り過ぎ、少しだけ離れた場所に座り込んだ。拳三つほど離れた距離は、遠くも無く近すぎも無い、微妙な距離だ。
膝を抱え、俯き、長い髪で顔を隠すようにした望美は、短くは無い沈黙の後に口を開いた。
「その……ちょっと暴れちゃって、部屋の中汚いんです」
だから見られると恥ずかしいんで駄目、と呟いてから、望美はようやく顔を上げた。
髪を無造作に掻き揚げる横顔は、まだ少し涙の跡を残している。赤さの滲む眦に、九郎は先程の胸の痛みが強まるのを感じる。それを誤魔化すように、九郎は懐から持ってきたものを取り出す。
「望美、これ。お前が落として行ったものだ」
顔をあまり見ないようにしながら差し出せば、躊躇いがちに伸びてきた手が受け取る。
「ありがとう、ございます」
視線を九郎へ向けぬまま、ぎゅっと胸元に抱き締める様を横目で眺め、九郎は僅かに姿勢を糺す。正面ではなく、真横に座る望美へとしっかり眼差しを向ける形で座り直すと、九郎は低く声を紡いだ。
「朔殿に習って、裁縫をしていたそうだな」
「え? う、うん。女の子らしい作業は、私に似合わないのは分かってるけど、ちょっとは出来るようになった方がいいのかなって」
望美は胸に抱いた布に視線を落とす。
白い布は手拭いを目指して運針したものである。生地はとてもいいものだが、縫い目はお世辞にも綺麗とは言い難い。
望美の生まれ育った世界ならば、こんな直線縫いなどミシンを使えば一発終了の世界で、ボタンを押して、曲らないように見守っていさえすれば完成するものだ。家庭科の才能にそれほど恵まれているとは言えない望美でも失敗する要素は極めて低い。
だが、電化製品など望めるべくも無いこの世界では、なんだって手作業だ。一針一針、こつこつと手を動かして縫うしかない。何度も針で指を刺し、布もぼろぼろにして、実際には三度目の正直とばかりに縫い始めたのが、今抱え込んでいる手拭いだ。最初の頃は朔がずっと見ていてくれたが、彼女がいると頼りすぎてしまいそうだ、ということで、ここ暫くは一人で黙々と仕上げていた。
大分出来栄えは良くなったとは思うが、朔の作る縫い目には遠く及ばない。
分かっていても、諦めずに頑張ったのは生来の負けず嫌いさに加えて、これを渡そうと思った相手の存在があったからこそ。望美はちら、と隣に座る人に視線を向ける。一瞬だけ眺めるつもりだったのに、真っ直ぐに向けられていた九郎の視線とかち合い、そこから顔が動かせなくなる。
「く、九郎さん?」
「大分前から、お前の手が傷だらけな事は気になっていた。何といっても剣を握る手の事だからな。だが稽古や怨霊退治に支障は出ていないようだし、きちんと手当てはしてあるようだったから、あまり立ち入った事を言うのも拙いだろうと考えていたんだ」
「そうだったんですか」
気付かれてないと思っていた、との呟きに、九郎は流石に苦笑する。
「お前の事だ。気付かないはず無いだろう」
「はぁ、そうですか――…って、は!?」
突如大声を上げた望美に、九郎は勢いに押されるように僅かに身を反らす。
「な、なんだ。どうした」
「や、その、あのですねっ」
片手で口元を覆う望美の顔が赤い。掌の下で口が動いている様子がちらりと見えるが、何を言っているのかは聞こえない。怪訝そうに首を傾げる九郎を上目遣いに見上げ、望美は深々と息を吐き、両手を床に突いた。がっくりと項垂れるような姿勢である。
「そーですよね、妹弟子ですもんね。不出来な後輩の面倒はきちんと見ないとですもんね」
望美が零す溜息混じりの声に、九郎は眉を寄せた。
「お前――本気でそれだけだと思っているのか?」
「へ?」
上げた視線が、至近距離に九郎の瞳を捉えた。形のよい眉の下で、強い色を宿した眼差しが真っ直ぐに望美の眼を見つめている。
「あの時、裁縫なんか等と言ったのは、お前の手の傷が許せなかったからだ。それでつい、心にも無い――いや違うか」
九郎の手が望美の指先を包み込む。緩やかに、だが有無を言わせぬ動きで持ち上げられたのは、未だ幾つかの針傷を残す左手だ。親指が、痛みを与えぬようにそろりと傷痕をなぞる。
「あの時は何故か、誰か他の男の為の縫い物だとしか、思えなかったんだ。だから、ついそんなものなど縫うなと、そう口走ってしまったんだ。落ち着いて考えれば、お前が自分で使うためのものだという選択肢すらあるのに」
「違…っ、あれは!」
慌てて言い募る望美に、九郎は小さく頷いてみせる。
「ああ。分かっている。というか、布の模様が見えてしまったから判った、というのが正しいんだが」
朔が布を畳みなおす時に見えた手拭いの柄。白地に淡い藍色で染め抜かれていた小さな紋は、源氏を示すもの。
名残惜しげに手を放した九郎は、頬どころか首筋まで紅色に染まった少女の顔を間近に覗き込み、涼やかに微笑んだ。
「まさか鎌倉殿に献上する品でもないだろう。他の誰でもなく、あれは俺のものだと、そう思っても構わないのか……?」
微量の照れを含みながらの問いへ、望美は無言で手に握りこんでいた手拭いを広げた。ばさりと九郎の首へかけ、そのまま布の端を両手で握り締めるとぐいっと引き寄せる。
「っ、なにを――」
流石に姿勢を大きく崩しはしなかったが、僅かに状態を望美の方へと傾ける形になった九郎の頬へ、ふわりと温かなぬくもりが触れる。九郎の耳だけに届いた甘い音色は、唇が離れる時の微かな水音。
「本当は、もう完成してるんです。ただ、渡す勇気が出なくて」
早口に言ってから手を離し、勢いよく立ちあがろうとした望美だが、寸前で九郎がその細い腰を攫う。膝上に抱き寄せられる形になった望美は、上がりかけた悲鳴を必死に飲み込んだ。
「く、九郎さんっ」
上がる動悸で途切れがちな声で名を呼べば、腰と肩を抱き寄せる腕にぎゅっと力が込められるのを感じた。
「ありがとう。大事にする」
「……うん」
耳元で囁かれる声は、柔らかく優しい響きに満ちている。
そろりと腕を上げ、望美は九郎の肩に手をかける。衝動的に頬に口づけなどした癖に、やはり恥ずかしくて抱きつく――までは出来ない。そんな逡巡を悟ったわけではないだろうが、間近で笑う気配が伝わってくる。
「誤解の無いように付け加えておくがな。大事にするのは、手拭いだけではないぞ」
九郎の声に思わず瞬けば、一言二言、甘い言葉が耳朶近くで呟かれる。
こんな言葉を聞くなんてこれは夢じゃないだろうか。驚きを胸中に閉じ込めた望美は、今度こそしっかりと九郎の首へ腕を回し、思いを伝えるように抱きついたのだった。
- END -
||| あとがき |||
最初は5月度の拍手お礼SSにしようと思ってたんですが…ちょっと長くなりすぎたので、もう少しだけ書き足して1万カウントお礼の話に代えさせて頂きました。