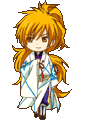想いを綴る言葉
2010.02.24
本編内、夏か秋。「ひらがなの思い」の続き
- 九郎×望美
「ずるいと思うんです」
素振りをする九郎を眺めながら、ぽつりと望美が呟く。
前振りもなく、突如として話を振ってくるのは望美の癖らしく、何事も筋道立て、順序良く話してくる己の旧友とは正反対だな、などと九郎は思う。
正直言えば、あまりにも唐突過ぎる会話は苦手ではあるのだが、望美に関してだけは慣れた――と言ってもいい。出会ってからそれほど月日が経つわけではないが、かなりの長い時間、共に過ごしているのだ。自然と話す機会も増え、同時に望美の癖に晒される時間も多くなるのだ。
とりあえず素振りを中断した九郎は、庭石に腰掛けている望美に向かい直った。
「何がだ」
「以前、九郎さんへの『お手紙』を書いたじゃないですか」
「あぁ……」
春に法王絡みの騒ぎで望美に『書かせた』書状の事を思い出し、九郎は曖昧に頷く。
「確かに貰ったが、それがずるいとどうつながるんだ?」
「私だって、九郎さんからお手紙が欲しいです」
軽く唇を尖らせ、拗ねたような口調で告げられた言葉に、九郎は流石に絶句する。
「なっ……お前、だって用事も無いのに手紙などかけるか!」
「でも、手紙をもらったら、返事を書くのは礼儀だって弁慶さんが言ってた」
「いや確かにそれはそうだが、何故弁慶がそんな事を言うんだ?」
本来追求するべき点はそこではないのだが、九郎はとりあえず気になったことから問いかける。勿論、心の奥底では、話を逸らす事で手紙の件を忘れてくれればいいという、些か後ろ向きな考えがあったのも事実である。
そんな彼の内心には気付かぬまま、望美は素直に九郎の問いに応じる。
「六条堀川にいる方から、お手紙を頂いたんですよ。私、全く覚えていないんですけど、なんか私たちが怨霊を封印したことで、その人の命を救ったらしくって」
「そうなのか」
「それで、弁慶さん経由でお礼状っていうのを貰って。でもまぁ、読めなかったんですよ」
「……まぁ、そうだろうな」
九郎は溜息混じりに頷く。
あの一件以来、多少は文字の練習を始めたらしいが、まだまだ望美の知識は少ない。ようやく幼子向けの平易な絵巻物が読み解ける様になった程度だ。武士からの書状など、象形文字にしか見えないのかもしれない。
「それで、弁慶さんに読んで貰って、ついでに返事を書くのも手伝って貰ったんです」
「弁慶が書いたのか?」
こくりと頷いた望美の表情は、どこかうっすらと怒りを思い出すような色を浮かべていて、九郎は訝しげに首を傾げた。
「どうした? その時に何かあったのか?」
「あったって言うか……、弁慶さんこう言ったんですよ」
望美は軽く咳払いした後、弁慶の声色を真似て口を開く。
「白龍の神子は、既に源氏軍で神格化されている面があります。その神子の字が、あまりに酷いようでは彼らの夢を壊してしまいますからね。朔殿に代筆してもらうのもいいですが、ここは一つ、剣の稽古で手を痛めているという事にして僕が代筆しましょう――、って」
案外そっくりな声真似に瞬きつつも、九郎は己の友人が言ってのけた内容に思わず苦笑する。
「弁慶の奴……まぁ気持ちは判らないでもないがな」
「判らなくたっていいですー」
ぷぅ、と頬を膨らませ、望美は文句をつける。
「だから『そんな風に言うなら返事を書かなければいいじゃないですか』って言ったら、返事を書くのは礼儀ですよ、って。あとは、それで軍の士気が上がるからと言ってました」
「なるほどな」
九郎は拗ねた口調を崩さない望美の前まで歩み寄ると、その形良く小さな頭にぽん、と己の手のひらを置いた。
柔らかな髪を乱さぬよう気をつけながら、労わるようにぽんぽんと軽く撫でる。
その労わりに満ちた仕草に薄赤く頬を染めながら、望美は九郎に言い募る。
「……だ、だからっ。それで思い出したんです。九郎さんから返事を貰ってないって」
しまった。きちんと思い出されてしまった。
九郎は内心で呟くが、表面上は何事でもないように、望美へ笑いかける。
「どうしても書状が欲しいのか?」
「え? ど、どうしても、絶対っていうわけじゃないんですがっ」
反射的に答えた後、望美は言い惑うように視線を逸らし、唇をチラリと舐めて潤してから言葉を継ぐ。
「九郎さんがどんな言葉を私にくれるのかなって、それが見てみたかっただけ、で、す」
思う事を告げては見たものの、途中から恥ずかしさが増したのか、語尾が曖昧に掠れ、望美も顔を逸らしたまま俯いてしまう。
その旋毛を見下ろしていた九郎は、すっと膝を折り、望美の顔と視線の高さを合わせる。
「どんなも何も――お前に言う言葉は、ただ一つしかないぞ」
目を合わせようとしない望美の頬を包み、ゆっくりと、だが有無を言わせぬ力を込めて己の方へ向けた。
陽光を映してきらきらと輝く翡翠を真正面から捉え、九郎は一つの言葉を紡ぐ。
「俺はお前が好きだ」
丸く大きく目が開かれるのに莞爾と笑い、何事かを問おうとした柔らかな唇の動きを封じるように口づける。
熱を分け合った時間はほんの僅かだが、その合間に望美の頬の紅色が九郎にも移ったようだ。赤く染まった頬を隠さぬまま、九郎は望美の耳元へ囁いた。
「貴族たちのように、美辞麗句で飾ってやる事は俺にはできん。だから、この言葉だけ、お前は知っていればいい」
- END -
||| あとがき |||
メールの返事を片付けながら思いついた話なので、なんかこう…あまり精度がよくないんですが、とりあえず暫く九郎さんも書いてなかったのでかいちゃえー! みたいな。