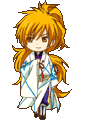埋められぬ隙間
2010.01.05
九郎×望美+将臣で、夏の熊野のお話。
- 九郎×望美
熊野で久しぶりに望美に出会った将臣は、再会にはしゃぐ彼女に付き合って勝浦を巡り、夕方宿まで送り届け――そのまま、八葉の仲間たちに「せめて夕餉だけでも共に」と懇願されて、つい時をすごしてしまった。
宿の縁側で月を見上げる将臣の隣には、望美が座っている。正確には、先ほどまで話をしていたのだが、昼間の疲れが出たせいか、ことんとスイッチが切れたように眠りについてしまったのだ。
「変わらねぇなぁ……」
再会した時は、随分と大人びた笑顔を浮かべるようになったと感じたものだが、こうしてみると、鎌倉で高校生をやっていた時と何も変わらないように見える。
「変わったのは俺の方か」
木の床に投げ出された望美の手は、触れそうで触れない位置にある。
この隙間が、たぶん今の二人の距離なのだ。
「悪ぃな。守ってやれなくて」
低く呟き、触れあえぬ距離のまま、将臣は再び月を見上げた。
濡れたように輝く月光は、見る時々によって穏やかさを感じたり、物悲しさを感じたりするから不思議だ、と将臣は思う。そんな風に空を見るようになったのは、多分この世界に来て己を救ってくれた男の影響だろう、と低く笑う。武士でありながらも雅な世界も常に忘れぬ同胞――今は遠い場所にひっそりと落ち延びていく平家の者たちを遠く思っていると、きしっ、と低く軋む足音と共に、小さいがよく通る声が彼の耳に届いた。
「将臣、そこにいたのか」
「ん? 九郎か」
肩に寄りかかって眠る望美を落とさないように気をつけつつ、声のするほうへ顔を向ければ、長い髪をゆらゆらと揺らしながら、姿勢のよい男が歩み寄ってくる所だった。歩く途中で眠る望美に気付いたのか、すっと足音が低くなるのは流石と言えるだろう。静かに、と合図しかけていた将臣は、黙って上げかけた手を下げた。
「何かあったか?」
「いや、宿の者が部屋を用意してくれたらしい。遅くなったし、泊まって行ったらどうだと思ってな」
「あー……、そうだな。そうさせて貰うか」
同行者がいるから、と一旦は断ったわけだが、ここまで遅くなっては自分の宿に戻るのも億劫だ。気ままな『弟』もどうせ適当に過ごしているだろうと判断し、将臣は九郎の誘いに頷いた。
「もしよければ、お前の連れの居る宿に使いを出すが」
「いいぜ、面倒だし。あいつも勝手にやってんだろ」
「そういうものなのか?」
「ああ」
豪放磊落に笑い、ふと将臣は表情を変える。
「九郎。話があるんだけど、今いいか?」
「別に構わないが、なんだ?」
「ま、座れよ。――ああ、こっちじゃない。そっち」
将臣の隣へ腰を下ろしかけた九郎へ、将臣は反対側を示す。
「は? だが、しかし」
「いーから」
座った座った、と促す場所は将臣の左側――の、更に先。彼に凭れる様にして小さな寝息を立てる望美の隣だ。
よく分からないながらも、根が素直に出来ている九郎は大人しく指示された場所へ座る。
「話とは何だ」
「んー」
がしがしと頭を掻き、将臣は九郎へ視線を向ける。
「単刀直入に聞くか。お前らって結局どうなんだ?」
「どう、って、何の事だ?」
「お前と望美の関係」
ずばりと言い切った将臣の言葉に、九郎は夜目でも分かるほどに顔を赤く染めた。
(やっべ、ヒノエや弁慶がからかいたくなるのも分かるわ)
その単純さに、思わず噴出しそうになるのを必死に押さえる。
「なっ、そ、それは!」
「しーっ。……ちょっと声押さえろよ。起きちまうだろ」
己の肩口へ視線を向けつつ指を一本立ててみせると、九郎は慌てて口を噤んだ。
「結局『婚約者』ってのは建前で終わってるわけ? それとも嘘から出たなんとやらになっちまったわけ?」
「待て、なんでお前まで婚約者の話を知っているんだ…ッ」
再び絶叫しそうになる九郎だが、今度はなんとか後半声を押さえる事に成功する。
「はぁ? 九郎、お前ばっかじゃねーの?」
呆れたというよりは、どこか憐れむような表情で、将臣は九郎を見る。
「法王始め、貴族の連中が居る前で堂々と宣言したんだってな? そんだけ派手にやりゃあ、いくら田舎に引っ込んでるに等しい俺だって耳にするぜ」
「そういうものなのか……」
「白龍の神子ってのも、大分知れ渡って来ているしな。まぁココでは主に、熊野別当が白龍の神子に入れ込んで追い掛け回してるっていうのが噂の原因ッポイ気もするけどな」
「確かに」
あちこちの町や村で聞いた噂話を思い出してか、九郎が苦い表情を浮かべる。
「で? 結局どうなわけ? 同じ青龍の加護を受ける仲間だぜ。誤魔化してもすぐに分かるからな」
さっさと吐け、と脅す言葉に背を押され、九郎は訥々と言葉を紡ぎだした。多分それは、同じ青龍だからという理由ではなく、望美に最も近しい幼馴染の男への敬意が過分に含まれているのだろう。途切れがちだが、どこまでも実直な響きが夜空の下に生まれていく。
「――婚約者と言うのは法王に望美を獲られない為の言い訳だ。でも、俺は一人の男として望美が好きだ。彼女も……その、好いてくれている、と、思う」
「なんだよ、その『思う』って」
喉を鳴らすようにして将臣は笑った。
「コイツの事だから、結構ハッキリと好きだの嫌いだの言ってると思うんだけど、違うか?」
「いや……違わない」
「じゃあ、なん――…」
「望美は」
将臣の言葉を遮るように、九郎が口を開く。
「望美、譲、それにお前もだが、この時代の者ではないだろう」
「まぁそうだな」
同意の頷きを将臣は返す。
「今はまだ方法が分からないが、その手段さえ分かれば、元の世界に戻るべきだ。望美の事は、その日まで大事に守りたい。そう思っている」
「あー、待て待て。守るのはいいけどさ」
将臣は片手をあげて、九郎の言葉を遮る。その表情は、望美さえ寄りかかっていなければ、もう片方の手で額を覆わんばかりのものだ。
「お前はそれでいいわけ? 元の世界にコイツが戻るってことは、もうお前とは二度と会えないって事なんだぜ。望美だって、傍にいない男をずっと思って独り身で居る保障なんか全くない。誰かいい男見つけて、恋をして結婚――じゃあ通じねぇか。祝言あげて、やがて子供を産んで……」
流れるように紡がれる将臣の言葉が、九郎の眼前へ突きつけられていく。
「お前を、忘れていく。それで平気なわけ?」
きつい事を言って居る自覚は将臣にもあった。
だが、そこまで言わなければ九郎の本音も聞けないし、自分の伝えたい事も伝わらない。そんな確信を抱き、将臣は厳しい言葉を投げつけるのだ。
「――平気だとか、平気ではないとか、そういった問題ではない」
酷く長い沈黙の後、ようやく九郎は口を開いた。
言葉を選ぶようにゆっくりと低い声で呟く。
「望美にお前を元の世界に戻す方法を探す、と約束をした。俺にはそれを果たす義務がある」
すいっと九郎の手が伸び、望美の頬に乱れかかる髪を払いのける。無骨な指先だが、その動きはどこまでも優しく柔らかい。
「望美が初めて人を斬った日を、俺は覚えている」
手の優しさとは裏腹に、九郎が紡ぐ言葉は重苦しい響きを含んでいた。
「源氏に加勢して戦った望美は、それまで何人も敵を――怨霊ではない生身の武士を斬っていた。大体は『これ以上戦えないように』するために、足を斬って動けなくしたり、手を傷つけて武器をもてないようにする。そんな風に戦っていたし、俺たちは――俺や弁慶、景時は、望美の戦い方はそれで良いと思っていた。最低限、己の身を守るために相手を倒してくれれば良いと、そう思っていたんだ」
「綺麗事だな」
「そうだ。――戦場でいつまでも、そんな事が通用するはずなどないのに」
将臣の言葉に、九郎は笑って頷いた。
「あの日、俺を守るために、望美は武士を斬った。鮮やかな一太刀だった。相手は苦しみすら覚えずに逝っただろうなと思う。――その時は、あまりにも普通にしていたから、気付かなかったんだ」
共に陣幕にいたはずの望美がいなくなったと、朔が九郎のところへ駆け込んできたのは真夜中の事。八葉で手分けして探し、藪の奥深い場所で彼女を見つけたのは九郎だった。
涙に汚れた顔で、吐くものが無くなるまで吐き尽くして、そのまま力尽きたように冷たい地面の上に昏倒していた望美。彼女の周囲に散った土は、その白い指先が掻き毟った痕だとすぐに知れた。
意識の無い身体を抱きかかえて戻り、弁慶と朔の介抱に委ねた後も、暫く九郎の脳裏から彼女の姿が消える事は無かった。
忘れていたのだ。
白龍の神子は、怨霊の前を離れれば、ただ普通の少女であるという事を。
どれだけ剣の腕が立とうとも、本来その切っ先が見詰めるべきは、生身の敵ではないのだという事を。
「そうやって心身共にぼろぼろなくせに、次の日は平気な顔をして笑うんだ。その取り繕った表情が、俺には辛い。――俺は戦うしか能のない男だが、望美は違う。全てが解決した後は、望美は『平和な世界』で生きるのが相応しいと思う」
口を閉ざした九郎は、そのまま視線を伏せて俯いた。
九郎の告白を聞き終えた将臣は、逆に視線を空へと向ける。
――平和な世界という言葉は曖昧なものだ、と将臣は思う。
自分たちが生まれ育った世界は、局地的に言えば平和な場所が多い。多分、望美が語って聞かせたのだろう「生まれれ育った鎌倉」の話は、九郎にとって夢のような場所に見えたのではないだろうか。
本当は、世界のどこかでは常に争いがおきていて、テロや戦争のニュースは、一日に何度もテレビから流れてくる。それだけではない。『平和』と言われる国ほど、なんてことのない理由で死者が生まれている。
多分その理不尽さは、この時空の戦よりも酷いものかもしれない。
どうなるか興味があったから、というだけで人ごみで薬剤を撒き散らし怪我を負わせる者。自分が生きていたくないから、と言う理由で他人を殺し死罪を願う者。そんな恣意的なもの以外にも、日常には思いがけない場所に危険や事故が潜んでいる。
その全てを九郎に説明する事は難しいし、間違いなく理解も出来ないだろう。
だから将臣は、九郎に伝わりやすい言葉を選んで問いかける。
「平和っつーけどさ、九郎は戦いを終わらせるために、望美を巻き込んで色々やってるんじゃねぇの?」
「勿論そうだ」
「じゃあ、その平和になった世界に望美を残らせる、っていう選択肢はないわけ?」
ひょいと指差しつつ問いかける声に、九郎は考え込むように眉を寄せた。
「……考えない、訳ではない。でも」
今日何度聞いたか分からない言い訳じみた言葉に、ぷつっと将臣の何かが切れた。
「あーっもう、ほんっと面倒くせぇな!」
九郎の言葉を遮り、将臣は深々と溜息をついた。
「分かった。もういい」
「何がだ」
「お前が望美を好きで、望美がお前を好きなら、素直に身を引こうと思ってた。でも、もうやめた」
肩に寄りかかり、静かに寝息を立て続ける少女の頬に手を添え、己の方へと強く引き寄せる。
「お前が『今の望美しか要らない』のなら、望美の未来は俺が奪う」
フェイクではない。
己の真実の願いを込めて、将臣は九郎に言葉を叩き付けた。
平和な世界、というものを九郎は想像でしか知らない。
いや、想像した事すらないと言ってもいい。戦が終わった後の事など考えた事すらない。彼にとっての世界は源氏であり、兄・頼朝で、兄の築く「理想の国」の為に戦って死ぬ事だけが、唯一で絶対の願いだった。
それに疑問を突きつけたのが、白龍の神子だった。
自分自身の心は、望みはどこにあるのだ? と、無造作にに九郎の心の中へ踏み入ってきた彼女は、それでも紡ぐ言葉に嫌味などは一切なくて、ただ純粋に九郎自身を思うが故に生まれた言葉なのだと全身で告げていた。
それはある意味乱暴ではあったけれど、頑なに生と死しか眼に写していなかった男の心を溶かし、彼に自信が歩む「道」を振り返らせた。
ただひたすらに、前を見据えて歩む姿は美しい。
だが、時にそれは破滅への道でしかない。
結果を問わず、そこから生まれるものを問わず、与えられた道筋を刻むだけの背中は、孤独という毒に冒されている。振り返り、己の足跡が残した物を認め、再び道を選んで歩み始める――それだけのことで、九郎の視界は大きく変わった。
髪の一筋、血の一滴すら源氏へ捧げていた盲目的な忠義は、完全に消え去りはしなかったけれど、大切なものは一つきりでなくてもいいのだと、彼は心の持ち様を変えたのだった。
大切なものは友であり、仲間であり、それから何よりも恋情を捧げた少女。それを「大事だ」と選び取る事に迷いはなかったけれど、九郎はまだ己の心を自由にすることに不慣れだった。こうあるべきだ、こうするべきだ、とガチガチに凝り固まった思考は、まるで牢獄のように九郎の心を閉ざしてしまう。
今、彼の心を縛り付けて居るのは「一度約した事は違えてはいけない」というもの。
――望美を元の世界に返すと、約束した事を果たさなければいけない。
自分がどう思うのか。また望美が……どう思っているのか。それらは全て二の次になっていた。
そして今、九郎を再び変えようとする言葉が、青龍の加護を共に得た相方から突きつけられていた。
「望美の未来は俺が奪う」
傲慢なほどの笑顔で告げた彼女の幼馴染の青年は、引き寄せた望美の顔へと己のそれを近づけていく。
「やめろ……!」
唇が触れ合いそうになる寸前で、九郎の手が割って入った。
ぐい、と望美の肩を引き、将臣の腕から彼女の細い体をもぎ取る。そして彼女の顔を自分の胸元へ隠すように引き寄せると、さらりと揺れた髪が一瞬遅れて九郎の指に絡みついた。
「ん…っ、…」
目覚める寸前のような、喉を鳴らすような声を漏らした彼女を強く抱きしめながら、九郎は低く威嚇の声を押し出した。
「望美に、触れるな」
払い除けられた手を中途半端に空へ浮かしたまま、将臣は九郎を見返した。
睨み返すのではない。純粋に、ただ視線を九郎へと向けたのだ。それに気付いて、九郎のほうも戸惑ったように数度瞬く。つい先程まで確かに将臣にあったはずの、彼を挑発するような空気はどこかへ霧散していた。
「……将、臣?」
探るように名前を呼べば、にやり…と猫のように口角をあげた笑みが返って来る。
「やっと本音を言ったな」
喉奥を鳴らすように笑いつつ、将臣は行き場を失った手を伸ばして九郎の額を指で弾いた。
「痛ッ!」
「これくらい我慢しろ。――大事なものを、預けるんだから」
弾いた指先でぐりぐりと九郎の眉間を押し、それからようやく手を離す。
その仕草は、時折望美が九郎に『顰め面しない!』と言いながらやってくるものに似ていて、少し九郎は複雑な気分になる。
「ずっとさぁ、大事にしてきたわけよ。産まれた時からの付き合いで、このままずっと、一緒にいるんだろうなぁ。一緒に居たいよなぁ、とか考えてたわけだ。……アイツは『有川のどっちと付き合ってるの?』とか聞かれても『どっちとも付き合ってない』『二人とも大事な幼馴染』って言い切ってたから、恋愛感情なんざ全く持ってないのは分かってたけど、俺は――いや。俺たちは、望美に惚れてたから」
だけどさ、と笑顔のまま将臣は言葉を続ける。
「俺たちが一番大事なのって、突き詰めて言えば望美が幸せで居てくれる事なんだよな。――だから望美の選んだ恋を、俺は応援する。でも無条件でじゃねぇよ。幸せになれないのなら、全力で止めるし、奪い返しもする。お前が本気じゃなければ、マジで奪い去っていくつもりだったぜ」
「つもり『だった』……なんだな」
過去形で語る事を指摘すると、将臣は片頬をゆがめるようにして笑った。
「あんだけ威嚇されりゃあ嫌でも分かるぜ。――さて、と。俺は飲み足りないから、もうちっと飲んでくるわ」
部屋ってあっちだろ? と指を差すのに、九郎は話題の変化についていけず、戸惑いつつ頷く。
「酒代、お前のツケな」
「俺が払うということか?」
言葉は分からないながら、なんとなく察して問えば、将臣は軽い調子で頷いた。
「そーそー。今日くらい、俺に飲ませてくれてもいいと思うけど」
「――今日だけ、だぞ」
将臣の意図を察し、九郎は苦虫を噛み潰すような表情で頷く。それほど長い付き合いではないが、将臣の酒豪ぶりは知っている。酔うまで飲むならどれほどの酒が居るのか、と思えば、多少は懐具合が心配にもなるのである。
それを分かっていて、将臣のほうもおどけて返事をしてみせる。
「おっ、ラッキー。言ってみるもんだな。撤回されないうちに厨に頼んでくるか! ついでにヒノエでも誘うかな~。一人酒は侘しいし」
身軽な動作で立ち上がった将臣は、ひらりと手を振って歩き出す。
「じゃーな、おやすみ九郎。あと、そこの狸寝入り娘も、いつまでもこんな場所で寝たフリしてると風邪ひくぜ?」
最後の最後に爆弾発言を落として歩き去る男は、角を曲るまで一度も振り返らなかった。
将臣の足音が遠く消え去ってから、ようやく望美が顔をあげた。
「……狸寝入りじゃないもん。二人が五月蝿いのがいけないんだから」
もそもそと眼を擦りながら訴える声は、まだ半分眠っているかのような舌足らずなものだったが、九郎を動揺させるには十分なものだった。
腕の中でまだ眠そうにしている少女を見下ろし、九郎は恐る恐る問いかけた。
「望美。お前、いつから起きていたんだ」
「ほんのちょっと前、ですよ。……ねぇ九郎さん」
「なんだ」
「好きですよ」
ぽつりと、確かめるような声で紡がれた言葉に九郎は僅かに息を詰めた。ぴくりと震えた肩の動きに気付いてはいたが、望美は構わず言葉を続ける。
「将臣くんの気持ちだって、ちゃんと知ってた。でも私は、九郎さんが好き。誰よりもす――」
続くべき言葉は不意に途切れた。どちらから仕掛けたのかは分からない。望美の言葉を聞きたくなかった九郎からか、それとも、同じ言葉を繰り返すより、実力行使に出たほうが思いが通じると思った望美からか。
だが、そんな些事はもうどうでもよくて。
短くはない時間重なっていた唇が離れた後、僅かに朱を刷いた頬のままで九郎が告げる。
「これ以上は言うな」
「どうして」
不満げに望美は睨む。
「どうしてもだ」
「嫌です。だって九郎さん何も言ってくれないから、ちゃんと伝わるまで私が言うんです。――好き。大好き」
「だから!」
もう一度、九郎は望美の声を遮るために顔を寄せる。先ほどとは異なり、深く絡む舌の動きに、望美は思わず九郎の着物に縋りつく。
「――お前が言ってばかりだと、俺が告げる暇がないではないか。それに、あれだけ言われて伝わってないわけないだろう……?」
馬鹿だな、と九郎は望美の下唇を親指でなぞる。
「俺は、好いてもいない女人に口づけるような趣味の悪さは持ち合わせていない」
「あ。そういうもの、なんだ」
「お前、俺をなんだと思っているんだ」
「よく言うじゃないですか、据え膳食わぬはなんとやらって」
「……」
よりによって、そんな事を言うか、と九郎は思わず天を仰ぐ。
自分の言葉が足りないのは薄々分かっていたが、ここまで理解されていないと、いっそ清々しさすら覚えてしまうのは何故だろう。
「じゃあ聞くが、お前はそれでいいのか?」
「いいって、なんですか?」
「俺がお前をなんとも思わずに、その……触れたりしても」
躊躇いがちな九郎の言葉に対して、望美の答えは潔すぎるほどにさっぱりとしていた。
「良いも悪いも、人の心なんてどうしようもないじゃないですか」
透徹な視線が九郎を正面から射抜く。
「私は、九郎さんに好きになって欲しいから、あなたを好きになったわけじゃない」
見返りが欲しいから恋するのではない。
己の心に素直になって、その気持ちを訴えているだけだと、望美は静かに微笑んだ。
「ただ、あなたが好きなだけ」
「俺には……よく分からないな」
神子であるが故の無償の愛なのか、それとも、望美の思いが一風変わっているのか。
今までに知ったどんな「想う気持ち」とも異なる彼女の主張に、九郎は戸惑うばかりだった。
「いいんですよ。九郎さんは九郎さんのままでいてくれれば、それだけで」
「本当に、不思議な奴だな」
九郎は望美を抱き寄せたままだった腕に力を込めた。
本気で力を込めたら骨が砕けてしまうのではないかと思うほどに華奢な体躯は、それでいてしっかりと肉もついていて、男には無い柔らかさと仄かに甘い体温を九郎に伝えてくる。
「俺は、お前のようにただ相手を想うだけでは満足できない。相手が幸せならそれでいい、と割り切ることが出来ないのもよく分かった」
望美のためと言い聞かせるようにしていたのは、きっと自分の恐れを認めるのが怖かったからだ。いつか来る別れに怯え、失うのではなく『自分から手放してやるのだ』と思い替えることで誤魔化そうとしていた。
(でもお前は俺の弱さも全て、受け止めてくれるのか)
今のままでいいと微笑む彼女の言葉が、九郎の弱さを前へ進む勇気に変えてくれる。
その言葉に背を押されるまま、九郎は熱の篭った言葉を囁きかける。
「お前だけを、愛している。――他の誰にも、奪われたくない」
「……うん。離さないで、下さい」
甘い声で告げられた彼女の願いを叶えるべく、九郎は抱きしめる腕に更に力を込めた。
- END -
||| あとがき |||
『九郎の恋のさやあてに将臣を使うのは、同じ青龍だからというのもありますが、うっかり弁慶やヒノエを連れてきたら奴らに言動で敵うはずがないと思うからです…。』
という風にmemoで書いたときの最終話に書きましたが、あかんわ。まさおにも勝てないよ(笑)。
というか九郎さんが誰かに口で勝てるなんて思う人は、どこにもいないか…。