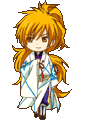夢の守人
2009.12.07
夏の熊野のお話。
- 九郎×望美
京を離れているから気が緩んだはずではない、と九郎は思う。だが、確かに六条堀川や京邸にいるときよりはやるべき仕事も圧倒的に少なく、怨霊退治も出来る範囲が限られているから、夜ともなれば暇な時間を持て余すのは確かなのだ。
今宵も、たぶんヒノエか将臣あたりが言いだした張本人だろう。夕餉の後、酒を酌み交わして男たちは時間をつぶしていた。
別に九郎とて酒が嫌いなわけではない。勧められるまま杯を煽り、心地よい酔いに浸る。ヒノエの伝手でか、運ばれる酒は極上と言っていい。つまみは譲が時折(主に将臣へ)文句を言いつつも、酒に合うものを用意してくれるので、ますます手が進む事になる。
夜半を過ぎ、気がつけば室に残っているのは九郎だけだった。
(将臣…は、譲を寝かせに行ったのだっけか)
他の者はどうしたのだろうか、と思えば、倒れ伏して寝ている者もいれば、大人しく部屋に戻ったか不在の者もいる。
「片付けは、明日やるか……」
この惨状を一人で片付けるのは口惜しすぎる。林立する瓶子を眺めて溜息をついた時、不意に視界が翳った。
大きく開いた入口に立ち月光を遮る人影へ視線を向けると、なぜかそこにいたのは長い紫苑の髪を揺らす少女。
「望美? どうした、こんな夜中に」
女性二人は男たちの酒宴には付き合いきれぬ――と温泉に入った後、さっさと床についたはずだった。
「……くろーさん」
どこか幼い声で名を呼んだ少女は、薄い夜着の肩へ袿をかけた姿で彼へ歩み寄る。どこかおぼつかない足元に、転倒を恐れた九郎は、膝を立て、彼女へ向けて腕を伸ばす。
「お前、どうした? 何かあったのか」
「甘えていい?」
「は?」
脈絡のない言葉に、九郎は手を伸ばした格好で硬直する。それを意に介さず、望美はふらふらと九郎の前へ歩み寄り、倒れこむように彼の腕の中へ身を投げ出した。
「ちょ、お前……!」
線の細い少女といえども、思いきりぶつかられてはそれなりの重量を感じるものだ。しかも九郎も酔いの中にある。辛うじて受け止めは出来たものの、姿勢の悪さもあり勢い余ってうしろへ倒れこむ。
したたかに打った後頭部の痛みで意識はずいぶんはっきりしたものの、逆に腕中の柔らかな身体を意識してしまい、九郎の鼓動が跳ね上がる。
倒れた拍子に幾つか瓶子を巻き込んだらしく、酒精の香りがじわりと二人の周囲に匂い立つ。その濃厚な香りか、それとも抱きしめた存在故か、九郎の頬がほんのりと赤く染まっていく。それを誤魔化すように、九郎は早口に口を開く。
「望美、おい、本当にお前どうしたんだ」
問いかけにも応えず、頑是ない子供のように彼の衣を両手で拳を作って握り締める彼女を見遣り、九郎は一つ溜息をつく。
飛び込んできた彼女を受け止めたまま、背に回っていた手のひらであやすように数度叩けば、くすんと洟をすするような音が胸元から聞こえた。
僅かにでも反応があった事に九郎はほっとし、静かに低めた声で囁いた。
「何があったのか話してみろ。なんでも聞いてやるから」
そのまま背を柔らかく撫でる仕草を続けていると、やがて望美が躊躇いがちに口を開いた。
「いやな夢を、みたんです」
ぽつりと呟きが落ちる。
「――九郎さんが、いなくなっちゃうの」
その囁きは、深い絶望に縁取られていて、鋭い刃のように九郎の胸を突き刺した。
それは孤独への恐れ。
何かを失う痛みを知るからこそ、九郎は理解してしまう。喩え夢だと分かっていても、存在を確かめたいときがあるのだと。
「馬鹿だな」
背に回した腕で、彼女を抱きしめ直す。
「俺はここにいるだろう?」
「ん……」
重なる身体は普段よりもずっと暖かく、まだ彼女が半ば夢の世界の住人であることを思わせた。
今の会話を起きた後に覚えていることはないだろうと分かっている。それでも出来るだけ優しく聞こえるといいと願いながら、九郎は望美に語りかけた。
「傍を離れたりはしない。だからもう寝ろ」
お前の眠りは俺が守るから、と耳元で囁けば、胸元から僅かに覗く頬が綻ぶのが見えた。
- END -
||| あとがき |||
時期で言うと、夏の熊野を舞台にSS書いてるのが多いような気がして来ました。なんというか、春より秋より夏が一番賑やかしく明るく平和で楽しい時期なのかなぁとか…。
そんな明るいはずの夏に、悪夢話ってのもアレですが(…)。
ところでこのまま二人とも寝ちゃったら翌朝大変ですね☆ とか思うんですが、あまり気にしない事にしよう。