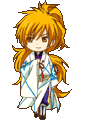未来への約束
2009.11.xx
恋愛ED(現代ED)後の二人。「ずっと、あなたと」の後日譚
- 九郎×望美
今日は九郎がこの世界へきて迎える、二度目の誕生日――の、数日後。
本当は当日に祝いたかったのだが、試験やらなんやらと学校行事が立て続けに舞い込んだ事に加え、九郎の方も仕事の都合があったりと平日に会うことが叶わず、ようやく祝う時間を取れたのが週末になってしまったのだ。
去年は照れとか色々なものも混じっていて、有川兄弟も巻き込んでの祝いに仕立て上げた望美だが、今年は素直に『二人っきりでお祝いしましょう』と九郎に宣言してきた。無論、九郎に否やはない。
本当なら甘いはずの時間なのだが、何故か望美は眉を寄せ、不満げな表情を浮かべている。
洋酒のきいたケーキを切り分けながら、ここ数日で幾度となく繰り返した問いかけを望美は口にした。
「九郎さん。お祝いに欲しい品物って本当にないんですか?」
「何度も言ったが、別にないぞ。――望美、茶はダージリンでいいのか? 他にはなんかよく分からんが、甘い香りのするのがあるぞ」
覚えているだけで両手の数を超えるだろう質問に、九郎は紅茶を用意しながら苦笑する。
「ダージリンでいいです。ねぇ九郎さん。本当の、本当に?」
「何度聞かれても同じだ。欲しい品物はない」
「もぅ。九郎さんって本当に欲がない人ですねぇ」
望美はケーキの皿を居間のローテーブルに置き、九郎の隣へすとんと腰を降ろす。
「そんなことはないぞ。物品ではないけれど、欲しいものはある」
「え?」
ぱっと顔をあげた望美の瞳は、絶対それを聞き出すぞ! という意思に満ちあふれていて、九郎は思わず笑みを誘われる。
こうやって自分のために一生懸命何かをしようと考えてくれる、それだけで本当は満足なのに、望美はなかなか信じてくれない。
(ああ、違うな)
信じる、信じないではない。
京にいる頃、個人的な願いを決して口に出すことがなかった自分へ『思うままに望んでいいのだ』と告げた望美は、その時の言葉そのままに、九郎の想いを引き出そうとしてくれているのだろう。
「物ではないが――強請ってもいいのならば」
笑顔で言葉を切った九郎は、隣に座る望美の手首をやんわりと握る。それを己の方へ引き寄せると、シャツの胸ポケットから取り出した物を彼女の指へ通した。小さな銀色の輪の中で、更に強く蛍光灯の灯りを弾き返すのは望美の誕生石。左手に収まった指輪を凝視した後、ゆっくりと望美は九郎を振り返った。
「九郎さん、これ――」
「求婚には、こうやって指輪を渡すのだと聞いた。縁を結ぶ指に留めてやるのだと」
静かだが、強い意志と決意を込めた言葉が、九郎の唇から紡がれる。
「欲しいのは、物ではないと言っただろう。俺が欲しいのは、お前の未来全てだ」
望美はただ呆然と九郎の瞳を見つめ返した。室内にはテレビの音や、マンションの外を通り過ぎる車の音が響いているはずなのに、彼の声以外、何も聞こえてこない。九郎は握り締めたままの手首を持ち上げ、己がつけた指輪の上へ口づけを落とす。
「まだお前は学生だし、すぐにとは言わない。大学にも行くのなら、そこを卒業してからでも全く構わない。今、約束をもらえれば何年だって待てると思う。だから――いつか、お前が納得できる時が来たら、俺の妻になって欲しい」
瞬きもせずに彼の言葉を聞いていた望美は、やがて悪戯っぽく笑って問い返した。
「それじゃあ、納得できるまで何十年かかっても、待ってくれるの?」
天然かどうかは不明だが、京にいる頃から相手の意図とずれた問いを投げてくる少女ではあったが、相変わらず今も、その気質は変わっていないらしい。
しかし九郎は、一瞬押し黙ったものの、前言を翻すような事はしなかった。
「……男に二言はない」
「武士に二言はない、じゃないんだ」
「本来はそういうのだろうが、もう俺は武士ではないからな」
お前に恋うるただの男だ、という言葉は胸の奥にだけ留めた。
彼から武士という肩書きを奪い取った少女は、紫苑の髪を揺らして九郎の首へと抱きついた。ぎゅっと腕を回し、驚いたように、だがしっかりと望美を抱きとめてくれた男の耳元へ、楽しげに囁きかける。
「ねね、九郎さん。前に私たちの世界の成人が二十歳だって言う話をしたこと、覚えてます?」
「覚えているぞ。確か京で俺の誕生日を祝ってもらった時だったか?」
耳朶に届く息に擽ったそうにしながらも、九郎は大人しく望美の言葉を促す。
「成人すれば、保護者の同意が無くても結婚できるんです。私は私の意思だけで、九郎さんに嫁ぐ事が出来るようになるんです」
紡がれる声が示すものに気付き、九郎は思わず彼女を抱く腕に力を込めた。
苦しいよ――と背を叩かれて、慌てて力を緩めつつ、無邪気に笑う望美の顔を覗き込んだ。向けられる視線を受け止め、望美は輝くような微笑と共に願い事を口にした。
「だから私、おねだりします。二十歳になったら九郎さんの姓を私にください、って」
俺の姓、と鸚鵡返しに呟いた九郎は、すぐに意味を察して目を見開く。
「それは――源望美として、生きてくれるということか?」
「それ以外のどんな意味があるんですか?」
細い指を伸ばし、望美は九郎の鼻をぴしっと弾いた。
「時空を越えてまで手に入れたかったあなたの事を、私が手放すわけないじゃないですか。束縛付与だって極めちゃったくらいなんですからね?」
「ははっ、そうだな」
偉そうに京で覚えた特技を語る元・白龍の神子に、九郎は屈託なく笑顔を返した。
「望美」
戦の前の様な、張り詰めた空気を孕む声が、静かに名前を口ずさんだ。
出陣の時や戦闘が始まる前、いつもそうやって彼が名前を呼んでくれた事を思い出す。最初は心配そうに紡がれていたそれは、季節を経る毎に信頼に満ち、伸びやかな夏空の元で新たな色彩を加え、秋の終わりと共に恋と言う実を互いの心に結んだ。
「なんですか、九郎さん」
「上手くいえないが、俺は本当に幸せだと思う」
「ふふふ、もっともっと幸せにしますよ? 覚悟して下さい」
「それは白龍の神子の預言か?」
「違います。ただの事実です」
望美は少し身体を離すと、九郎の顎先に小さく口づけた。
「お誕生日おめでとうございます。来年も、その先も、お祝いを一番最初に言う権利は私のものですよ」
「勿論だ。お前の時は、俺が最初に祝うからな」
「はい!」
一片ずつ花弁を重ねていくかのような約束は、どこかこそばゆくて甘い。
そっと重ねた薄紅の唇が、鮮やかな笑みを象って揺れる。
それは彼の傍で麗しく咲き誇る、永遠の花。
- END -
||| あとがき |||
この話を思いついたのは仕事中で、今、実は印鑑関連のお仕事をさせて頂いていた時に、結婚のお祝いに印鑑を~とかいった文章を書いていて「ああ、そういえば姓が変わるもんなぁ」とかぼんやりしていて――九郎さんの姓を私にください、のヒトコトが降ってきたのでした。