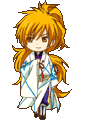柿の日
2009.10.26
恋愛ED後の現代 秋のとある日のお話。
- 九郎×望美
「こんにちは、九郎さん。これ、お土産です」
チャイムを鳴らすと同時に合鍵を使ってアパートのドアを開けた望美は、出迎えた九郎に向かって大きな袋を差し出した。
「なんだ?」
反射的に受け取った九郎は重みのある袋に首をひねる。
手早くブーツを脱いだ望美の、期待に満ちた視線に促されるように中を覗き込む。上を覆っていた布を払えば、中から現れたのは秋の味覚とも言える果実。
「柿ですよ、柿。今日は『柿の日』なんだってテレビでやってたんです。だからそれ見たら九郎さんに会いたくなって買ってきちゃいました」
「ふむ柿の記念日があるとは……今の時代はすごいんだな」
「え、記念日じゃないですよ。柿の日、です。九郎さんは法隆寺って知ってますか?」
キッチンへと向かっていた九郎は、望美の言葉に眉をあげて振り返る。
「馬鹿にするな。それくらいは俺とて知っている」
その勢いに、真後ろを歩いていた望美は、彼の背にぶつかりそうになってたたらを踏む。
「えっ、違いますよ! どっちかっていうと、私がいつ出来たお寺か知らないから確認しただけですよ」
「そういう意味か。すまない、勘違いした。――そうだな。確か厩戸王が建立したという話だから大体四、五百年は前に作られたのではないだろうか」
「うまやど……?」
聞き慣れぬ名に、今度は望美が首をひねる。
「知らないか。では聖徳太子といえば分かるか?」
「それなら分かります」
こくこくと望美は頷く。
二つだけ手元に残して残りの柿を冷蔵庫に入れると、九郎はキッチンナイフを手に取りながら言葉を継ぐ。
「厩戸王は聖徳太子の別の名だ」
「九郎さんが義経の名前を持っているのと、似たような感じですか?」
「…………いや全く違うが、まぁそこはどうでもいい。それで、法隆寺がどうしたんだ?」
話が長くなると悟った九郎は、話を最初へと引き戻す。
「そうでした」
器用に柿を剥き始めた九郎を見て、望美はキッチンにある食器棚から皿を取り出す。続いて一本だけフォークを取り出し、皿の脇に置く。九郎は柿を丸齧りするので、フォークは望美しか使わない。
「正岡子規って言う人が作った俳句で『柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺』っていうのがあるんですね。それが作られた日を元にして『柿の日』って決めたみたいです」
「へぇ……風流なものだな」
綺麗に八等分に切った柿を皿へ落としながら、九郎はぽつりと呟いた。
「俳句が、ですか?」
「いや。俳句というものの良し悪しは俺にはよく分からない。元々和歌のやり取りも苦手だったしな。ただ、なんというんだろう」
考えるように一瞬だけ目を伏せてから、九郎は再び口を開く。
「こういった何気ない日々にも、何かを結びつけ祝ったり偲んだりするような習慣は、平和な証なのだなと思ったんだ」
その声のはらむ深い響きに、望美は思わず隣に立つ九郎の顔を見上げた。しかし、目に映る彼の表情はとても穏やかで、その静かさ故に、望美は唐突に不安に駆られて九郎の身体へ腕を回す。
「おい、危ないぞ!」
使い終えたナイフを卓上へ下ろしかけていた九郎は、突然抱きついてきた望美に叱責の声を向ける。
「ごめんなさい」
謝りながらも、更に巻きつける腕へ力を込めた少女のつむじを、九郎は困ったように見下ろした。
「――おい、望美? どうしたんだ」
問いかける声も、自然と低く、相手を気遣う色をはらむ。
「なんでもないよ」
「全く、なんでもないって訳ないだろう」
微かに覗く横顔は、淡い憂いに満ちていて、九郎の動揺を誘う。
柿の汁がついた手をキッチンペーパーで拭うと、九郎は抱きついている彼女の腕はそのままに、正面から向かい合うように身体をずらす。そして己の胸元へと望美の頭を抱き寄せ、その頭頂へこつんと顎を乗せた。
「俺は弁慶みたいに聡くもなければ、ヒノエのように細かい事に気付いてやれる性質でもない。本来なら、恋人の事くらい、黙っていても分かってやれるべきなんだろうが、俺には無理だ」
「うん……そうかも」
「おい、そこは少しくらい否定したらどうだ」
即答する望美に向かって苦く呟いてから、九郎は再び口を開く。
「だからな。思った事があればちゃんと言ってくれ。聞いても、すぐに納得できるかは分からないが、お前の言うことならば俺は理解したいし、きちんと分かってやりたいと思うんだ」
九郎は望美を抱き寄せる手に力を込める。
人の体温が肌に伝わる熱だけではなく、心の奥底まで暖めてくれる事をいまの九郎は知っている。その喜びを彼にもたらしたのは、いま腕の中にいるかけがえの無い少女だ。
(彼女が与えてくれるぬくもりと、同じものを己は返せているだろうか?)
時折、九郎はそんな自問を繰り返す。
己の生きた時空を離れ、望美の生まれ育った時空へと移り住んで半年以上経つ今でも答えは出ない。それでも、ただひたすらに強く思うのは、彼女と共に生きるためには努力を厭わないということ。
「誰よりも、お前の事を知る男でありたいと願う。それが『共に生きる』ということなんだろう?」
「そう、ですよね」
九郎の胸元へ頬を摺り寄せた後、望美はゆっくりと顔をあげた。
「うん。分かった。話しますね。笑わないで聞いてくださいね」
「ああ聞こう」
「平和とか、そういう事を九郎さんが言うとね。鎌倉の事を――あの戦の事を思い出しているのかなって。もしかしたら、あの時空へ戻りたいのかなって……そう思ってしまうんです」
「それは違うぞ!」
即座に否定した九郎へ、望美は透明な笑顔を向ける。
「うん、分かってる。ただ、時折不安になるんです。本当にあの世界を九郎さんに捨てさせて良かったのかって。だけど、もう惑わないよ」
先ほどまで不安に揺らいでいた望美の表情が、九郎の見つめる中、ゆるやかに変わっていく。花開くような笑みは、それを受け取る九郎の心に陽だまりのような温かさを連れてくる。
「ごめんね。そしてありがとう。九郎さんはこんなに真面目に私に向かいあおうとしてくれているのに、不安ばかり抱えていちゃ駄目だよね」
「いや構わないさ。ずっと一人で考え込まれるのは困るが、こうやってお前の色んな表情を見るのは悪く無い気分だ」
明るい声で笑った九郎は、望美の額に軽く口づける。
「すまない。お前を不安にさせていたのは、俺にも原因があるんだろう。だが今日からは共に変われるな」
「はい、変わりましょう」
微笑みあい、自然と顔を寄せて唇を合わせる。
「――柿がきっかけで、私たちの記念日が出来ちゃいましたね」
長い口づけの後、少し目元を薄紅く染めた望美が囁く。
「記念日?」
「この後も、多分喧嘩したり文句言い合ったり、絶対色々あると思うんですよね。でもこの日の事を忘れなければ、すぐに仲直り出来そう。だから今日の気持ちを忘れないよっていう意味で『記念』の日」
「ははは、そうかもしれないな」
望美の言葉に、九郎は楽しげに頷いた。
「俺達だけの『柿の日』だな」
- END -
||| あとがき |||
10/26は「柿の日」だそうです。
朝、はな●るマーケットで見て(…)「あ、これネタに使おう」と思ったのはヒミツです。