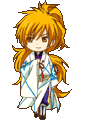恋でなくとも。
2009.10.18
夏の熊野でのお話
- 九郎×望美
後白河院に会った時、その傍に控える怨霊が化けた女房を観察しよう! 等と思わず、さっさと撤退するべきだったのだ。
「……ねー、九郎さん」
甘酒の注がれた杯に口をつけながら、望美は隣に座る男の名を呼んだ。
「なんだ」
「どうしてこんな事になっているんでしょうね、私たち」
「俺に聞くな」
「だって他に話しかける人、居ないじゃないですか」
「なら、静かにしてろ」
「くろーさんってばー」
「いい加減静かにしろ!」
ようやく九郎が望美の方を振り返った。
眉間には皺が出来、目元には明らかに疲れの色が滲んでいる。普段人前、特に貴族のお歴々がいる場所でそんな表情を見せることの無い九郎にしては、極めて珍しいことであった。
(もう、九郎さんずっと不機嫌だし、周囲の視線は痛いし、ほんっと落ち着かない!)
勝浦で出会った法王は、九郎の傍に望美――彼の許婚である白龍の神子がいることを認めた途端『祝いの席を設けてやってなかった』などと言いだし、あれよあれよという間に宴席をしつらえてしまったのである。
「要するにさー、暇つぶしだよね」
「いやそのなんだ、これは院のご好意のは――…、すまん、俺も否定はできん」
扇で口元を隠して欠伸まじりに呟けば、苦渋の応えが返ってくる。
主賓として祭り上げられてしまった二人は、他の八葉と引き離され、法王に程近い上座に座らされている。
八葉や白龍たちは、それぞれに心配そうに見つめてくるが、あからさまに不快を示す表情や、笑顔の裏に何か黒いものが混ざっちゃってる人は、それを向けている方向が九郎なのでまだ良いとして、いいネタを見つけたとばかりに面白がっている幼馴染の電波をバッチリ受信してしまった望美は、落ち着かないやら、居たたまれないやら、散々なのである。
「あぁん朔ぅ~。どうして貴女はあんな遠くの方にいるのー。九郎さんより朔の隣でご飯食べたかったよぅ。『ほら望美、これおいしいわよ、あーん』ってやって貰いたかったよぅ」
「……おい、問題はそこなのか」
「もちろん現実逃避してるだけです」
きっぱりと言い、望美はつまらなさそうな表情のまま膳へ箸をつけた。
「そんな風にでも思わなきゃ、食べてる気になりません。――あ、これおいしい」
甘い煮付けが気に入ったのか、ぱあっと翡翠の瞳が輝く。
「お前、言っていることの辻褄が合っていないぞ」
嘆息した九郎は、自分の膳にあった小皿を望美の前に置いてやる。
「ほら、気に入ったのなら食べろ」
酒を飲みながらだが、告げられた言葉が思いのほか優しかったので、望美はびっくりして九郎を見つめた。
「明日は雨? それとも槍?」
「なんだそれは。白龍の神子の予言か?」
生真面目に聞き返す九郎へ、望美は朗らかな笑い声を向ける。
「違いますよー。こっちでは使わないのかなぁ。誰かが意外な事をした時に、良く言う言葉なんですよ」
「とりあえず褒め言葉ではないわけだな。そんなに意外だったか?」
「意外っていうか、そんな分かりやすい優しさを向けてもらった事がないから。大体、会話の八割は、喧嘩じゃないですか? 私たちって」
酷い事をさらりと言ってから、望美は渡された皿を九郎の膳に戻した。
「おい、何をしてるんだ」
「嬉しいですけど、美味しいから九郎さんにも食べて欲しいです。だから返却」
「俺は別に――」
「いらん、じゃなくってですね」
片手をあげて九郎の言葉を制する。
「美味しいものは、皆で『美味しいねぇ』って言って食べる方が美味しくなるんです。譲くんのご飯を、皆で食べると美味しいでしょう? それと同じです。今は九郎さんしかいないから、九郎さんが食べてくれなかったら、私と気持ちを共有してくれる人がいなくなっちゃうんですよ。分かりましたか?」
にこにこと長口上を述べた望美を見遣り、九郎は暫し沈黙した後深く息を吐く。
「面倒な奴だ。というか、お前もしかしなくても酔ってるな?」
九郎の飲んでいる酒とは違い、望美に注がれているのは酒精の低い甘酒だが、それでも酒は酒。口当たりのよさに騙され量を過ごせば、勿論酔いも回ってくる。
ちらと見遣れば、瓶子の中味はかなり減っているようだ。
法王の反応や、周囲からの視線に気を取られて、望美の酒量を気遣わなかった事を九郎は反省した。
「これ以上飲むのはやめておけ。宿酔になるぞ」
「殆ど飲んでないのに、酔うわけないじゃないですか」
頬を膨らませながら再び杯を口に運ぶ望美の手を、九郎はやんわりと掴み取った。
「いいから、もうやめておけ」
低く窘めるように告げると、望美の手を己の口元へ引き寄せ、くいっと一息に杯を呷る。
「……甘い」
心底嫌そうに呟いてから、掴んでいた手を離す。
「よくこんなものを何杯も飲めるな」
「美味しいんですよ。っていうか、ひとのもの飲まないで下さい!」
「飲むなと言ったのに聞かないからだろう」
「じゃあ九郎さんのお酒下さい。それで許してあげます」
「馬鹿、こんな強い酒、お前にやれるわけないだろうが!」
「九郎さん、しーっ」
口の前に一本指を立てた望美の仕草に、九郎はぐっと拳を握って堪える。
(冷静に、冷静に。相手は酔っ払いだ)
念仏のように唱えてから、膨れ面の少女へ向き直る。
「とにかく、だ。明日に響くし、身体にもよくない。どうしてもっていうなら、その……なんだ。朔殿ではないが、お前のやりたかった……、あれ、をだ。やってやるから、我慢しろ。頼むから、酒はもうやめてくれ」
途切れ途切れに、物凄い言い淀みながら告げられた言葉は、不可解すぎて一瞬望美の脳裏を素通りする。
「はい? 何をですか?」
ぽかんと九郎を見返した望美は、真っ赤に染まった彼の顔を見て、きっちり四十五度首を傾けた。そのまま『朔』をキーワードに今日の会話を思い返す。
――これおいしいわよ、あーんって……
(えええええ!)
口を両手で押さえ、なんとか叫びを噛み殺す。
(ま、まさか、九郎さんが「あーん」とかやってくれるっていうの!?)
それは恥ずかしすぎる。なんていう羞恥プレイ。
目を白黒させ始めた望美の様子から、言いたかったことが理解された事を察し、九郎はぷいっと顔を背けた。耳元どころか首筋まで薄赤い彼の様子に、望美は込み上げる笑いを扇で隠した。
(なんて可愛いんだろう、この人は)
恋ではない。
それでも、愛しいと思う心は、確かに生まれている。
許婚という言葉を許容してしまうのは、そんな気持ちがあるから。
「ね、九郎さんも、絶対酔ってるでしょ」
「甘い酒がいかんのだ」
「じゃあそういう事にしてあげますから――」
九郎の袖を引いて振り向かせると、望美は柔らかく潜めた声で願いを口ずさむ。
「ここから帰ったら、柿でも一緒に食べましょう? あーんはしなくても、許してあげます」
「……あぁ、分かった」
短い返事と共に頷いた九郎の顔から、宴席の間ずっと消えなかった眉間の皺がなくなっていたので、望美は知らず満面の笑みを浮かべたのだった。
- END -
||| あとがき |||
なんかまとまらない話になってしまった…。
九郎さんが望美の手を掴んで、彼女の手にある杯をくいってやるシーンが浮かんだので、それを実現するためだけに書いた話です。