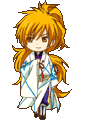ひらがなの思い
2009.10.11
本編・2章後半(舞イベントの後)のお話。
- 九郎×望美
「あー! 筆文字って難しいよ!」
そう叫びながら望美は紙をぐしゃぐしゃと丸め、力任せに壁へ向けて投げつけた。
彼女の周囲には、そうやってポイ捨てされたものがバラバラと散らばっている。反古にされた書付に囲まれながら、望美はぱったりと机に突っ伏す。
「こんなことなら書道の授業、もっと真面目にやっておくべきだった……あと古典とか」
溜息をつく理由は、弁慶が言った一言から始まる。
『望美さん、お願いがあるんですけど』
朝食後に声をかけてきた弁慶の笑顔がいつも以上にキラキラと輝いていたので、腹黒軍師め、またなんか無理難題を持ってきたな――と望美は思ったのだった。
「神泉苑であった雨乞いの儀式で、後白河院に対して、九郎は君の事を許婚と言って誤魔化しましたよね」
「あー、そういえばそんなこともありましたっけね」
望美はこくりと頷く。
「過去を振り返らない君の姿勢は美しいですが、つい一昨日のことですから忘れないで下さい。それで院がですね、九郎の許婚はどんな和歌を贈ってくるのか、とか余計なことを気にしまして」
「うっわ、ホント余計なことですねー」
悲しいことに、先の展開が読めてしまった望美は遠くを眺めながら溜息をついた。
「そんなわけで、九郎の為と思って書いていただけませんか?」
弁慶が背後に隠していた包みをそっと望美の前に差し出す。
促されるまま包みの結び目を解けば、中から現れたのは紙束の山。紙が貴重といわれる時代においては、かなり大盤振る舞いといえる量だ。
「とはいえ、君に和歌を作れと言っても無理でしょうから、古い恋歌を写すことにしましょう。添える花は時期ですし桜にして、焚き染める香は景時のところから貰ってくれば大丈夫ですね。というわけで、あとは望美さんの字だけです。せめてある程度『読める字』が書けるように、頑張って練習して下さいね」
ね? のあたりの笑顔が本当に満面の笑みだったので、だから望美はつい言ってしまったのだ。
「弁慶さん、もしかして楽しんでません?」
「おや、いけない人ですね、僕を疑うなんて」
「……」
するりと距離を詰めた弁慶は、望美の髪を指先に絡めとるようにして小首を傾げてみせる。
「純粋に君と九郎の事を心配しているのに……どうしたら信じてもらえるんでしょうね」
しまった、なんか分からないけど熊野男のスイッチを入れてしまった。
――こういう時の対処はただ一つ。
「と、とりあえず練習してきますね!」
望美は大急ぎで紙束を抱え、一目散に逃げ出した。
自室へ逃げ出して、素直に書き物の練習を始めてはみたものの、『お習字』は遅々として進まなかった。
震える手で筆を持って紙へ滑らせると、真っ白な紙にするすると墨が染みていく。迷い迷い書いているせいか、ぼたぼたと水溜りのようなしみが出来ていく。
「不細工だなー。ボールペンとかシャーペンなら、もっとマトモなものが書けるんだけど」
自分でもがっかりして、望美はぐしゃぐしゃっと書いたものの上にバッテンを描き、更に『べんけーさんのバーカ』と書いてから紙を丸めた。それを肩越しに後ろへと放り投げ、ごろんと床に仰向けに倒れる。
「そもそも、なんて書いてあるのか分からないままに真似しろっていうのもねー」
不機嫌に呟きながら、手本となる短冊を睨みつける。
柔らかい仮名文字で書かれた和歌は、漢字ばかりの文章に比べればまだなんとか読むことが出来る。でも、読めたところで、その意味が分からないのである。どこで区切っていいのかも、ちんぷんかんぷんだ。
「うつつには、さも…そ、あら……? うーんわかんない!」
短冊を抱えてごろごろと床を転がっていたら、不意にごつんと何かにぶつかった。
「痛っ…、って誰?」
額を押さえながら顔を上げると、呆れたような瞳が彼女を見下ろしていた。
「あれ、九郎さん」
「何をしているんだ、お前は」
文句を言う視線が微妙にずれているのでなんだろうと思えば、短いスカートが捲れ上がって白い太股がバッチリと顕わになっていた。
「あっ、すみません」
慌てて裾を直しつつ起き上がる。視線を戻した九郎は、彼女の向かいに腰を下ろすと、照れを誤魔化すように近くにあった紙つぶてを拾い上げた。
「こんなに散らかして。これじゃ弁慶の事を言えんぞ、お前」
「弁慶さんは終わっても片付けない人ですけど、私は終わったらちゃんと片します」
「そうか。とりあえず、きちんと整理して捨てるようにな」
適当に頷いた九郎は、手の中で転がしていた反古にされた紙を無造作に開き始めた。
「あっ、ちょっと九郎さん! 見ないで下さいよ!」
「ん? 大丈夫だ、お前がなんでこんなに紙だらけにしているのかは知っているし、お前の字が汚いのなんか今更じゃないか」
「いや、問題はそこじゃなくてですね!」
「それとも何か、見られて困ることでも書いてあるのか?」
何気ない言葉に、望美の動きがぴたっと止まる。
「いやまさかそんなことはハハハ」
「書いてあるんだな」
呆れたように告げると、九郎は開きかけた紙を望美の手に押し付けた。がさり、と二人の手の間で乾いた音が起きる。
「ほら、返せばいいんだろう?」
「……見ないんですか?」
「見られて困ることなんて、どうせ弁慶の悪口かなんかだろう」
なんでバレたんだろう、と望美は中途半端に開きかけた紙を見下ろす。その頭に手を載せた九郎は、苦笑まじりに望美の髪をかき回した。
「あいつに見つからない内にちゃんと処分しろよ」
「はーい」
頷いた望美は、力任せに紙を丸めようとして、思い直したように丁寧にそれを畳んだ。四回ほど折ってから自分の隣に置いて、改めて九郎を見上げる。
「ところで九郎さん、何か御用でしたか?」
普段から忙しくて、大体いつもこの時間は六条堀川の邸で執務をしているはずなのに、わざわざ九郎が来たのは用件があってのはずだ。
望美のへたくそな書を見に来たわけではない。断じてない、と思いたい。
「ああ、それなんだがな」
望美の内心の葛藤には気付かず、九郎は爽やかな声を紡ぐ。
「お前に変な事を頼んでしまってすまないと謝りたかったのと――もう和歌を書く練習などしなくていいと言いに来たんだ」
「え?」
不思議そうに望美は瞬いた。
「最初はな、院が納得――いや違うな。院が喜んでくださるような和歌でも見繕って書いて見せればいいだろうと思っていた。だが、それにどんな意味があるんだろうって、思い直したんだ」
「意味、ですか? 正直妙なこと思いついたなぁあの方は、とか思うし、面倒くさいことさせるなとか思いますけど、でも九郎さんが困ったことになるのは嫌だし、意味があってもなくても、私頑張って書きますよ。時間は……かかりそうですけど」
最後少し言いよどんだ望美の様子に莞爾として笑い、九郎は首を振った。
「ああ、分かっている。お前はそういう奴だ。だけど、お前にそんな無理をさせてまで院の機嫌を取る必要なんてないんだろう。俺は院のご機嫌取りの為だけに京にいるわけではないんだ」
「いやそれはそうかもしれないですけど、でも源氏の立場――はどうでもいいけど、何も持っていかなかったら、九郎さんがあちこちで怒られたりとかしません?」
源氏はどうでもいい、という科白には少し眉を寄せたが、九郎はそこには敢えて触れず、後半部分にだけ返事を寄越した。
「いや、何も持っていかないとは言っていないぞ。お前が書いてくれたものは持参する」
腕を組み、ほんの少しだけ目元を赤くしながら、それでも九郎は堂々と言い放つ。
「お前は――白龍の神子は、この時代の常識に囚われる必要などないと思う。だから、お前が俺の為にと書いてくれたものならば、どんなものだって胸を張って持っていく。誰にも文句など言わせない」
「九郎さん……」
不覚にも九郎の言葉に感動した望美だが、うっとりと両手を胸の前で組みかけて、はたと我にかえる。
「でも、何書けばいいんです?」
和歌を練習し無くてもいいのは嬉しい。
だが、その代わりに何を書けと言うのだ?
疑問をぶつけられた九郎は、気まずげに視線を横に流した。
「それは……お前が考えろ」
「九郎さんも一緒に考えて下さいよー」
九郎の腕を掴んでゆさゆさと揺する少女の手を、九郎は振り払いこそしなかったが、呆れたように大きく溜息をついた。
「お前なぁ、俺が貰う文の内容を、なんで一緒に考えねばならんのだ」
「だってどうせダミーじゃないですか」
「お前が使うみょうちきりんな用語の内容には触れずに置くが、だっても何も、その…あれだ」
「なんです、ちゃんと言ってください」
あ、まるでこの言い方弁慶さんみたいー、黒い成分が移るーとか考えていた望美は、彼の腕を掴んだままだった手が、温かいものに包まれたのに驚いて己の手を見遣る。
九郎の手が、そっと重ねられていた。
「……俺が、読みたいんだ」
ちらりと九郎の顔を見上げれば、完全に視線は明後日の方へと向いていて、長い髪の合間から覗く耳元が、驚くほど赤く染まっていた。
「なんでもいいから、書いてくれないか?」
「分かりました」
望美は手を動かし、彼の指に絡めるようにしてきゅっと握り締めると、慌てたように振り向いた九郎に笑いかけてから手を離した。
「今から書くから、見ていてくれますか?」
「ああ、見せてもらう」
目を合わせ、小さく笑みを交わす。
望美は九郎から離れて卓に向かいなおると、放り出していた細筆を手に取った。彼女の隣に移動してきた九郎は、緊張の面持ちで望美の手元を見つめる。
「本当に、なんでもいいんですね?」
「男に二言は無い」
力強く言い切る様子に後押しされて、望美はゆっくりと筆を動かす。
紙の中央よりやや左から、書きなれた『横書き』で文字を綴る。
黙って文字を追っていた九郎は、その不可解な書き順に眉を寄せていたが、文字を追い続けている内に、再び顔に熱が集まるのを感じた。
「望美、お前……」
最後まで書き終え筆を置いてから、望美は墨痕も鮮やかなそれを九郎の前へ滑らせた。
「ちゃんと考えて、書いたよ。九郎さんに伝えたいこと」
頬を赤く染め、堂々と宣言する。
ちょっと不恰好で丸っこい、女子高生風にいうなら「丸文字」で書かれたそれは、たった七文字のひらがな。
―― くろうさん すき ――
「よ、読める? ひらがなだったら大丈夫かなって思ったけど、いまの時代の仮名文字とは違うんだっけ」
あまりにも九郎が反応を寄越さないので、望美は不安になって問いかける。あまりにもドキドキしすぎて、胸が張り裂けそうだ。
「大丈夫だ、ちゃんと読める」
かすれたような声で答えた九郎は、望美の肩へ腕を回す。力を入れて引き寄せれば、抵抗無くすとんと凭れかかってくる。首筋まで真っ赤に染めあげた少女を胸の中へ抱き寄せると、彼女と同じくらい真っ赤になった頬を藤色の髪に摺り寄せて呟いた。
「俺も、好きだ」
- END -
||| あとがき |||
昔の人っぽい文字を書こうとするから、望美が筆で書く文字が汚いんだと思ってます。
好きなように、それこそボールペン字みたいに書けば、読める文字は書けるのではないかと妄想してみたりなんかして。