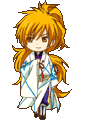吐けない弱音
2009.10.03
本編2章あたりをイメージしたお話。
- 九郎×望美
今日も今日とて、少女の絶叫が、京邸に響き渡る。
「九郎さんの馬鹿っ!」
日々鍛えた豪腕から繰り出された物体は、九郎の胸元に見事に命中する。割れ物ではないが、結構な質量のあるそれは、一瞬ではあるが、九郎の呼吸を止める。
そうして、引き止める言葉が出せずにいる内に、彼らの神子はくるりと踵を返し、どこかへと走り去ってしまった。
「……今日も絶好調ですねぇ」
嵐が過ぎ去るのをにこやかに見守っていた弁慶が、九郎の肩に手をかけながら慨嘆する。
「お前、見ていたなら止めろよ」
「ああなった彼女が、朔殿以外の言う事を聞くとでも?」
怒り狂う望美を、白龍の神子を止めることが出来るとしたら、それは恐らく彼女の愛する半身である朔だけだろう。
世界の真理を突きつけた男から、九郎は無言で目を逸らした。そんな彼に微笑みかけると、弁慶は友人の顔から医師の表情になって九郎の顔を覗き込んだ。
「ところで痛みは無いですか、九郎」
「ああ、大丈夫だ。――だが、これはなんだ?」
望美が投げつけた『何か』は手の中に納まるほどの大きさをした茶色の物体。
「木彫りの、器か?」
投げつけてきたとはいえ、望美が持ってきたものだ。いつ来るかは分からないが(それこそ彼女の気分次第だが)、会った時にちゃんと返せるよう、分かりやすい場所に置いておくべきだ。
そう考えて、近くの飾り棚へと手を伸ばしたのだが、その動きを止めさせたのは弁慶の問いかけだった。
「九郎、開けてみないんですか?」
「何故開けねばならん」
むっとしたように、九郎は弁慶を睨み据える。
「これは望美の持ち物だろう。人の物を勝手に見る趣味は無いぞ」
「それは見てもいいんですよ」
「どうしてだ」
理解できないといった態で、彼は首を傾げる。
「これは望美さんが、九郎のために持ってきたものだからですよ」
飾り棚に置かれた器を取りあげた弁慶は、ぽんと九郎の手のひらに載せる。小さく軽い重み。黙って己の手を見下ろす九郎へ、どこか諭すような口調で語りかけた。
「望美さんは、いつもよく分からないことで怒ったり騒いだり、正直僕らの理解を大きく超える女性ではありますが、今回に関してだけは、僕は望美さんの言う事も正しいと思っています」
「お前、それはあいつを擁護しているのかけなしているのか、全く分からんぞ」
「僕はちゃんと理解しているので大丈夫です」
さらりと応じ、弁慶は九郎へ背を向ける。
「おいっ、弁慶!」
すたすたと室を出て行く弁慶は、外へ出る一歩手前で振り返った。
「とりあえず君がやるべき事は一つ。その中味を見て、彼女が持ってきたものが何か理解することです。それからどうするかは、君自身で考えて下さい」
では御前失礼、と慇懃に礼をして、弁慶は歩み去る。
残された九郎は眉を寄せ、暫く弁慶に言われた事を咀嚼するような表情を見せてから――こわごわと、望美が残したモノの蓋をあけた。
それから四半刻後。九郎は京邸をうろうろと歩き回っていた。
「朔殿まで不在とは……」
朝から所用で出ていると、邸の下働きの者から聞いたとき、本当に九郎は困惑したのだ。
「全く、あいつはどこにいるんだ」
こうしてみると、彼女の事を知っているようで知らなかった事を気付かされる。
九郎と喧嘩した望美が逃亡する先は、ほぼ十中八九、朔のところである。それでなければ、譲のいる厨だ。
譲は那須与一との鍛錬の為に不在だった。丁度彼が外出する時に、入れ替わりのように九郎が京邸へ到着したのでしっている。
望美は、あの元気すぎる神子は、激しい怒りをどこで癒しているのだろう。
室は全て巡りつくした。
「あとは庭か」
小さく呟き、美しく木々の整えられた中庭へと足を向けた。
新緑へと移りつつある風景は心和むものだが、伸びやかに枝を伸ばす木々に茂る葉は、人探しの場合には行く手を遮る壁となる。無意味に探しては時間がかかるだけだ、と九郎が真っ直ぐに足を向けたのは、庭の奥のほうにある小さな広場。井戸へも程近いこの場所は、九郎と望美が剣の稽古をする場所でもある。
――居るはず無い。九郎に怒りを覚えて去った先が、彼と縁強い場所であるはず無い。
でも、其処にいてくれたらいいと、そう願うのだ。
複雑な気持ちを抱えながら茂みを掻き分けた九郎は、開けた視界の中、馴染んだ稽古場の片隅で蹲る少女を見つけて息を飲んだ。
九郎の視線の先で膝を抱えぐじぐじと洟をすすっている少女は、来たくてここに来たわけではなかった。他に行く場所が無かったのである。
朔は夕方まで帰らない。譲もきっと帰りが遅いだろう。午後から鍛錬に出たときは、源氏の人たちに引き止められるのか、夕餉を共にしてくる時がある。
無条件で甘えを許し、我侭めいた愚痴を受け止めてくれる人が今日はいない。
本当は室で不貞寝するつもりだった。それなのに、気付いたらこんな場所で座り込み、みっともない泣き顔を晒していた。
(馬鹿だ、私)
今朝もここで九郎と剣の稽古をした。
いつもと変わらない様子だったから気付かなかったのだ。彼が昨晩、怨霊との戦いで手傷を負っていた事を。――そして怪我したことを、望美に隠そうとしていた事を。
(知ってたら稽古なんかしなかったのに)
稽古を終え、汗ばんだ服を取り替えて朝餉の席へと向かう途中、ふと聞こえてきたのは景時と九郎の会話だった。姿は見えない。恐らく角を曲がった先にいるのだろう。
彼ら二人でいるときは源氏の軍議をしているときもある。邪魔しちゃいけないなと思い、自然と息を潜める。
「九郎、おはよう。怪我は大丈夫なのかい?」
「しっ、景時」
「あ、ごめん。……そうだった」
慌てたように息を飲む景時の声が、低く潜められる。
「聞こえてないよね」
「大丈夫だろう。先ほど室に戻ったばかりだからな」
誰、とは言っていないが、彼らが話題にしているのが自分なのはすぐに分かった。普段弁慶などに『本当に君は馬鹿ですね』とか言われている癖に、どうしてこういうときだけ、直感が働いてしまうのだろう。
彼らに気付かれないよう、じりじりと後ずさった望美は、その足で弁慶の元へと押しかけた。望美の評する所の営業スマイルで出迎えた弁慶に向かって、拳を握り締めながら告げる。
「傷薬が欲しいんです」
「えっ、どこか怪我でもしたんですか?」
途端慌てたように腰を上げる弁慶に、違います違います、と急いで両手を振る。普段容赦なく色々言って来る弁慶だが、体調管理にはうるさい。仲間たちの体調不良や怪我にいち早く気付くのも彼だ。それはやっぱり彼の優しさだと思っているので、望美は慌てて否定の言葉を続ける。
「私じゃなくて、く――…っ、ええと、なんでもないです」
えへ。と精一杯可愛らしく見えるように笑って見せるが、それで騙される弁慶ではない。核心に迫る言葉をさらっと口にする。
「九郎の怪我、ですか?」
果たして少女は、諦めたように頷いた。
「弁慶さんは知っていたんですね」
その瞳に、ほんの一滴の悔しさが滲んでいる事を弁慶は分かっていながら、冷静に言葉を紡ぐ。
「僕は薬師である前に、源氏の軍師です。源氏の大将が手傷を負ったとして、それを知らずにいるわけにはいきません。行軍や作戦の立て方に大きな影響が出ますからね。だから九郎は、僕には必ず話します。軍を率いる者の責務として」
「――はい」
分かっています、と頷く望美の頭を撫で、弁慶は少しだけ口調を変える。冷徹な軍師から、神子を支える八葉としてのそれに変わった音は、柔らかな響きで望美の胸に届く。
「でもですね。あんな九郎でも君の八葉なわけですから、神子である望美さんに何も言わないのは道理が通らないんです」
「それは……九郎さんが私を信頼していないから、言ってくれないんですか?」
口にして、痛みが胸に突き刺さる。
あの清冽な人が向ける視線が想像した通りだとしたら、と考えるだけで、胸の奥底が凍りつくような気がする。
「違いますよ。本当にしかたのない人ですね、どうしたら、そんな事を思いつくんですか?」
やれやれといった風に首を振り、弁慶は望美の顔を覗き込んだ。
澄んだ色の瞳に映る自分の顔を見つめ、望美は泣きたくなる気分を必死に堪えた。
「九郎はですね、あなたに心配をかけたくなかったんですよ。自分が怨霊との戦いで怪我をしたと知れば、望美さんが九郎に負い目を抱くだろうって、そう思ったんですよ。まぁこういうところが、九郎も大概格好付けで馬鹿な子なんですけれど」
「ええ、ホント、馬鹿ですね」
「九郎も君に言われたくはないでしょうが、本当に馬鹿だと思います」
「――あの、弁慶さん、一体誰の味方なんですか」
「馬鹿な子ほど可愛いっていう言葉、ご存じないですか?」
答えにならない言葉を吐いておいて、弁慶は「ですから」と続ける。
「傷自体はそれほど深くは無いので、一日二日でふさがる程度です。だからこそ九郎は、望美さんに気付かれない内に治してしまおうとしたんですよ。幸い、今日は休養日ですから、外に出る事もありませんし、治療に専念できます」
「そう、だったんですか……」
望美はこの室を訪れた時とは異なる意味で拳を握り締めた。
来た時は、ただの勢い付けだった。
今は?
「それで望美さん。傷薬、どうなさいますか?」
「あ」
そうだった。
「すみません、さらっと忘れてました」
「ふふ、君のそういう何か決めたら一直線なところは大好きですよ」
「素直に忘れっぽいなこの小娘とか言ってくれて構いませんよ」
「いいえ、君を好きなのは本当ですよ。――心配したからこそ、来てくれたんでしょう? 九郎を大事に思ってくれて、ありがとうございます」
自虐的に呟いて見た内容へ、ど直球の言葉が返ってきたので、望美は挙動不審なほどに視線を泳がせた。
「お、おも、思うっていうか、その……」
あたふたと手を握ったり開いたりを繰り返す望美を見下ろしながら、ああ本当に馬鹿な子ほど可愛いなぁ、と弁慶は相変わらずろくでもないことを考え、それでも、彼女が答えを出すのを沈黙のなかで待ち続けた。
「私は白龍の神子で、九郎さんは八葉で、八葉は神子を守り助けるのが役目だと思うんだけど」
「はい」
短く、だが言葉を続けるのにどうしても必要な相槌をくれる弁慶の優しい声に促され、望美はたどたどしくも、己の気持ちを口にする。
「そうしたら、八葉たちのことは誰が守るんだろうって……思ってしまうんです。九郎さんもだけど、譲君や弁慶さん、景時さんや……まだ見知らぬ仲間全員です」
珍しく弁慶は、どんな言葉を彼女に投げかけるべきか迷った。その一瞬の迷いを越えて、異世界から来た少女は、彼女自身の答えをそっと弁慶の前へ伸べてみせた。
「だから私は――…」
さくり、と下草を踏む音に気付き、望美は顔をあげた。
涙でぐしゃぐしゃになった彼女の顔は、本当に乙女かって思えるほど酷いものだったが、九郎は笑ったりしなかった。
手の甲で涙を拭う仕草を見てみぬ振りをしつつ無造作に歩み寄った九郎は、望美の隣へ腰を下ろした。望美の右側、しかし真横ではなく少し斜め――彼女の顔を見ない角度で。
「九郎ひゃん」
くすん、と洟をすすり、望美は九郎の横顔を見遣った。
「手を出せ」
振り返らないままで九郎は言う。
泣き続けた事で大分思考力が低下していた望美は、言われるままに手を差し出した。その手のひらの上に置かれたのは、見覚えのある塊。
「あ……」
望美は濡れた瞳を瞬かせ、手元へと帰ってきた木の器を凝視する。
「お前のものだろう?」
耳に届く九郎の声は思いのほか柔らかくて、まるで子供を宥めるような声だなぁとか思ったけど、それだからこそ、望美は素直に自分の気持ちを口にした。
「昨日、九郎さんが怪我したって聞いて」
前を向いたままの彼は応えを返す事は無かったが、望美は構わずに言葉を続けた。
「弁慶さんに教わって薬を作ったんです。本当はそれを渡しにいったはずなのに、なんか九郎さんの顔を見たら、怪我してて痛いんだろうに全然普通にしてるから、ついカッとしちゃって……。物、投げたりしてごめんなさい」
「お前の行動が突拍子ないのは、もう慣れた。――いや、そうじゃない。慣れとか、そんなのじゃなくて、……怪我の事を黙っていて、俺も悪かった」
長い髪を揺らして振り返った九郎は、もう一度すまない、と言って頭を下げた。
「心配をさせたくなかったのも本当なんだが、怪我をした事をお前に知られたくなかったんだ」
「どうしてですか?」
「それは……っ、その、情けないだろう。お前に剣を教えている身なのに、傷を負うなど。武士としてだらしないではないか」
歯切れ悪く、ぼそりと言われた言葉に、望美は面食らったように九郎の顔を見つめた。少しだけ見える彼の目元は薄赤く染まっている。
「情けなくなんかないです」
薬の入った器を持つ手で、九郎の服の袖を握り締めた。あまりに強く掴んだので、服の袖には皺が残ってしまいそうだったが、そんなの知ったことか、と神子様は嘯く。
九郎が怒るならばあとで洗濯でもなんでもしてやろうじゃないか。やり方はよく分からないけど、景時さんに聞けば大丈夫だ。だからそんな瑣末時より、伝えなければいけないものがある。
天性の勘、または野生の直感と言うべきもので、望美は今この時に必要な言葉を紡ぎだす。
「九郎さんはちっとも情けなくなんかないです。いつも八葉の先頭にたって戦ってくれて、不慣れな私たちを守ってくれて、すごく格好いい人です。私のいた世界の源義経もすごい人でしたが、九郎さんだって断然すごいと思ってます。……ただまぁ、もうちょっと石頭なところを直して、もーすこし融通が利けばいいのになぁ~とか思ったり思わなかったりもしますが、それでもですね、そんな九郎さんが私を庇ってうっかり怪我しちゃうのは嫌なんです。九郎さんだけじゃなくて、他の皆もそうです。守ってくれた結果私の身体に傷は残らなくても、誰かが痛い思いをするのは駄目なんです」
一息に言った望美は、真っ向から九郎の目を見つめた。
「だからもう少し、私の事も頼って下さい。八葉が白龍の神子を守るのが務めならば、私は八葉の皆を守りたい」
「望美……」
泣いた後で長い科白を口にしたせいか、少し望美は息切れしてしまった。はぁはぁと肩を揺らして息を吸った。その様子を、九郎はただただ無言で見詰めている。
言葉が無い様を呆れられたかと解釈し、望美は慌てて付け加える。
「あ、勿論今すぐにとは言いませんから。まだまだ頼りない神子なのは確かですし」
とりあえず、九郎さんを鍔迫り合いで吹っ飛ばせるくらいまでは成長しないといけませんね、と不穏な笑みを望美は浮かべる。
そして、ややあって思い出したように、握り締めていた袖を離すと、改めて九郎へ薬を押し付けた。
「まぁそんなわけで、傷薬を作ったんですよ。九郎さんを守るのは難しいかもしれないけど、一人で痛みを我慢させるのとかって嫌なんです。あっ、ちゃんと弁慶さん監修で作ってますから、薬効バッチリですよ」
口に入れるものではないから、これでもとりあえず大丈夫でしょう、という消極的な許可だった事は、墓場まで抱えていくべき秘密だ。
「それじゃ、薬使って下さいね。お大事に」
「待ってくれ」
立ち上がりかけた望美を引き止めたのは九郎の声。腰を浮かしかけた所で呼び止められたので、再び望美はぺたんと座り込む。
「お前、自分で言うだけ言って完結するのはやめろ」
呆れたように告げ、渡された薬を再び望美へと差し出す。
「う、受け取り拒否!?」
「そんなことするわけないだろう。折角だから――手当てしてくれないか」
「え?」
ぽかんと口をあけて九郎を見返す少女の姿は、やっぱりなんだか阿呆面で、さっき九郎を感動させたのは別人じゃないのかとか思わないでもないのだが。
これこそが、彼の神子なのだ。
今までであったどんな女人とも違う、破天荒極まりないこの少女こそが、九郎が守りたいと思った相手なのだ。そして黙って守られてくれるような娘じゃない事は分かっていたはずなのに、無駄に誤魔化して格好つけてしまったのは己の弱さ。
左袖をまくり腕を晒した九郎は、傷口を覆っていた布を解く。殆ど塞がりかけている傷痕は、薄赤い跡を一筋、彼の肌に刻んでいる。
「お前が言う通り、八葉は白龍の神子を守る。でもそれは義務だからじゃない。俺が……俺達が望んでやっていることだ。だからお前の事を庇うなと言われても、それは聞いてやれん」
きっぱりと言い切る九郎の目は真剣だった。だから望美は頷くしかなかった。
「だが傷を隠したりして、お前を不安にさせるような事は二度としないと誓う。それでは駄目か?」
「駄目じゃないです!」
渡された言葉は望美が願うものからは少し離れてはいたけれど、それでもよかった。
九郎が向けてきた笑みは青空のように晴れやかで、それを見ているだけで望美も自然と笑顔が浮かんでくるので、ああ、嬉しいなぁと素直に思えた。
傷の手当てを始めてみれば、手つきが乱暴だの布の巻き方が粗雑だの、他愛も無い口喧嘩が始まるのだが、それはもう些細な事。ただ春風だけが、二人のやり取りを見つめていた。
- END -
||| あとがき |||
今回のタイトルは、恋したくなるお題配布さまの「版権お題」内『九郎風味のお題』より頂きました。
お題の「吐けない弱音」は、九郎のやせ我慢(別名・男のプライド)と言う感じで。
ついでに望美までぐじぐじ悩んじゃったのは、筆が滑っただけです。
イメージ的には、2回目か3回目のの運命上書き中くらいで、まだまだかよわい神子時代(どんな)という風に思っていただければ幸いです。