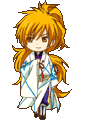絡める指先
2009.10.01
京邸にいる頃を想定したお話です。
- 九郎×望美
ぎぃん、と鈍い音が響く。
鋼と鋼がぶつかり合う音は、朝の涼やかな空気を切り裂いて、一つ、二つ…と鳴り渡る。
音の主は、九郎と望美。それぞれの得物を持ち、鍛錬というにはやや物騒な斬りあいを続けている。何しろ使う武器は、怨霊との戦いで使っているそれだ。刃は時に服の端を掠め、揺れる髪を風に舞わせる。
そんな訓練は危ないと止める者もいる。
またはせめて使うなら木刀にしろという者も。
だが、こうやって常日頃使う武器を手に馴染ませることで、戦場で生き延びる確率が上がることも確か。神子を大事に思うからこそ、結局は彼女の望むまま、鍛練を続けるのを八葉たちは許容することになった。
太陽が最初の光を地表に投げる頃から、その身をすべて青空に晒すまでの僅かな時間、彼らは激烈に剣を交わす。
二人の師であるリズヴァーンを交える事もあるし、極々稀にだが、将臣が混じる事もあった。だが、望美ひとりで練習をすることだけはなかった。
望美が一人で鍛錬する事を、九郎が嫌うからである。
白龍の神子を一人にするわけにいかないとか。
一人でやらせたら絶対怪我をするに決まっているとか。
景時の邸を破壊されてはたまらないとか(未だ建物は壊していないものの、木の枝を折ったことは何度となくある前科持ちなので、望美は反論が出来ない)、そんな多彩な主張はあるが、結論としては「独りきりで剣を振るうな」に帰結するのだ。
そこで「じゃあ誰かが一緒ならいいんですよね」と望美が言うのは当然のことで、いつの間にか、彼女の訓練は九郎が責任を持って指導する……という風になっていたのだ。
「何故、俺が」
最初のうちこそ、そうやって文句を連ねていた癖に、他人に指導者の立場を譲ったり押し付けたり、はたまた手抜きや鍛練拒否といったことがないのは、九郎の生真面目さが現われている。同じ師を仰ぐ兄弟弟子としての責任もあるに違いない、とは敦盛の弁だったが、やはりそれにも望美を含む他の面々は大きく頷いたものだ。
……だがしかし、ヒノエや弁慶あたりからすれば「無自覚って罪だよな」「自覚がないからこそ、こういう独占欲をさらっと言えるんですよ」という会話で評されるような事柄でもあるのだった。
一際高い鋼の噛みあう音の後、鍔迫り合いを弾き飛ばす形で望美を後退させた九郎は、すっと刀を降ろした。
「今日はこれで終わるぞ」
「え? あっ…はい」
崩された体勢を直し、再度打ち込もうと身構えかけた望美は、九郎の声に驚いたような声をあげ、それから改めて大きく息を吐いた。
動いている間は気付かなかったが、手を止めると程よい疲労感が腕まわりに漂っている。
今日も京で起きている怪異を捜し歩くのだから、疲れ切ってしまう前に止めるのは当然のことだ。
(すごいなぁ、九郎さん)
ただひたすらに、夢中になって後先無く剣をふるってしまっていた自分がちょっと恥ずかしくなる。
それでも、と望美は思うのだ。
それくらい集中してやらなければ、九郎に相手をしてもらう価値などない。
だって源九郎義経という人は、とてもすごい人だ。
時に剛直にして、時に流麗。舞うような足捌きで華麗な太刀筋を見せたかと思えば、細身ながらも鍛えられた体躯から繰り出される剣は、重く激しい奔流となって相手に襲いかかる。
口に出して言うのはムカツクし、言う気もさらさらないのだが、リズ先生だけではなく、この人に鍛えてもらっている自分は、とても幸福だと思うのだ。
「は~、お疲れ様でした。今日もありがとうございました」
剣を鞘に戻し、深々と頭を下げる。
丁寧というよりは、疲れでガックンガックンと動いているように見えるのはご愛嬌。
「昨日よりだいぶ剣筋が安定しているな。この調子を忘れるなよ」
同じく太刀を腰に戻しながら講評を口にした九郎は、不意に片手を前に出す。
「望美、手を見せてみろ」
「え、何でですか? というか、右? 左?」
疑問を呈しつつも、なんとなく従ってしまうのは、最早、習性のようなもの。
これがヒノエあたりだったら『何をされるか』と警戒する所だが、九郎に限ってそのような心配は要らないと分かっている。
「右だ」
問いに答えるより早く伸びてきた九郎の手が、望美の手首を掴み取る。
その仕草は無造作だが、触れられる望美自身に痛みは全く無い。
ふわり、と称するに相応しい柔らかさで手を取られ、指先が彼の視線の高さまで引き上げられる。
「く、九郎さん?」
「ああ、やっぱり傷になっているな」
手首を掴むのとは逆の手が、そっと望美の指をなぞる。
「んっ……」
ぴりっとした痛みが走り、望美は小さく声をあげる。
「すまん! 痛かったか?」
慌てて触れた指をひく九郎の動きに導かれるように、望美は自分の手をじっと見つめた。
痛みがなかったので気づかなかったが、指の関節付近の皮がうっすらと剥け、血が滲んでていた。
剣の稽古を初めた当時は、あっという間に手が真っ赤になり、擦りむけたり肉刺になったり、もしくは血肉刺へと変化したりして、どんどん手はボロボロになっていったものだ。だが、数ヶ月もすれば、手のひらの皮膚は硬くなり、ちょっとやそっとでは傷つかなくなった。
乙女としては『ちょっとどうよ?』と思わないでもないが、この手のひらは、彼女が戦場に相応しい――八葉たちと戦うのに相応しい姿になった証であり、刻んできた日々の答えだった。
だから、ちょっと哀しくはあるものの、傷だらけの手を恥ずかしいとは思わない。
そんなわけで、怪我も勲章といった気分の望美だが、練習で手が傷つくのは少々久しぶりであったのでびっくりしたし、それに本人より早く気付いた九郎はすごいと感心するのだ。
「大丈夫ですけど……でも、やっぱりって?」
「途中から右手の握りが甘いような感じがしたんだ」
手首でも傷めたかと思ったが、そうではないようだったし――と九郎は答える。
「すごいですねぇ、九郎さん。打ち合っててよく分かりますねぇ」
感心したように望美は呟くが、あれっ? と首を傾げる。
「でも『手首を痛めたかも』とか思いつつも、最後すっごく容赦なかったですよね」
思いきり跳ね飛ばされた時のことを持ち出して、望美はじとっと九郎を上目づかいに睨む。
「それは、手首の怪我ではないのはすぐに分かったから……」
答えながらも、あまり良い言い訳ではないと思ったのか、九郎の口調が珍しく尻すぼみになる。
どんな時も、明朗に、言いにくい事もずばっとすっぱり告げてくるのが九郎という人なのに。
(珍しいなぁ)
そんな思いが視線に現れたのか、まっすぐに向けられた瞳を見て、どこかたじろぐ様に、九郎はほんの僅かに目を反らした。
「その、……悪かった。怪我をしているのではないかと疑っているのに、ああいうことをするものではないな。――お前とする鍛練の時間は楽しくて、つい夢中になってしまうんだ。お前のことは、大事にしてやりたいと思っているのに、ちゃんと考えてやれず、すまない」
やや早口に言われた謝罪はともかく、後半に続いた告白めいた科白に望美はかっと耳元が赤く染まるのを感じた。
一方の九郎はと言えば、言葉の途中から反らした視線を戻し、真正面から望美のことを見据えていた。その迷いのない姿勢が、彼が真実、心から言葉を紡いでいるのだと知らしめる。
(このっ…天然成分過剰男めっ!)
掴まれている手首までが熱い。
内心で九郎を罵倒しつつ、それでも口に出さないのは、言われた言葉が嬉しかったからだ。つい心の中限定で文句を浮かべてしまうのは、どう考えても恋だの愛だのいう理由で、九郎が口を開いているわけではないと思っているからだ。
(大事っていうのは、白龍の神子だからだよね!)
女の子として大事にしてたら、真剣で斬りあったり、言い合いの末に殴りあったり(いやこれは訓練関係ないか)、そんな事はしないはず。
少なくとも望美が男だったら、好きな子とそんな事はしたくない。
(うん、そうだそうだ)
そんな結論を脳内で下し、気づかれないように深呼吸してから、常と同じ口調を心がけて答える。
「大丈夫ですよ! 私、若いし、頑丈だし!」
それでも心に閉ざした熱が伝わってしまうのが怖くて手を引こうとするが、九郎はそれを許してくれない。それどころか、更に手を引きよせ、傷口をまじまじと眺めている。
「痕は残らないと思うが、とりあえず簡単に手当てをしておくか。その後弁慶に見てもらうといい」
そんな事を言いながら、懐から布を取り出そうとするので、望美は慌てて自由な方の手を横に振った。
「いえ、その、弁慶さんに布巻いてるのうっかりと見つかると、問答無用で痛い薬塗られるだろうから、心より! 本気で! ご辞退申し上げたいでござる――!」
「……お前、言葉が変だぞ」
「そんなことありません、ハハハ」
「弁慶の治療が、そんなに嫌か」
「嫌っていうか」
目をあちこちに彷徨わせたのち、諦めたようにはぁ、と息を吐く。
「だって沁みるんですもん。にこにこ笑って、痛い薬塗るんですよ? 大丈夫って言ってるのに、そりゃあもう遠慮なくグリグリと」
眉を寄せて答える望美に、九郎は朗らかな笑い声を投げた。
「そういう反応をするから、弁慶が面白がるんだろうに」
「九郎さん~、あの虐めっ子軍師様、どうにかして下さいよぅ」
「俺にどうにか出来ると思うか?」
弁慶は人あたりの良さで誤魔化しているが、人の好き嫌いが実は激しい。どうでもいい相手には作り笑いで誤魔化して、完全無欠の軍師様を演じて見せるのに、何故か望美には、最初から全開で感情を(相手にとってありがたいかは別として)ぶつけまくっている。
だから、むしろ彼を『どうにか』してしまうのは、白龍の神子である望美本人だろうと思うのだが、彼女の認識は違うらしい。
「出来なくても、して下さい。私の平穏のために」
「無茶を言うな」
ざっくりと切り捨て、九郎は取り出しかけた布は懐に押し込めた。
どうせ今手当てをしなくても、目ざとい弁慶は彼女の傷を朝餉の終わる頃までには発見し、治療を施すだろうことは間違いない。
それなら、とりあえず今は彼女の希望通りにしてやるのもいいだろう。
そんな甘やかしな九郎の考えに気づかない望美は、彼が布を取り出すのをやめたことでほっとしたように笑顔を浮かべる。
「もうホント、手の傷なんていつもの事だし、こんなの、舐めとけば治っちゃいますよ」
――いつものこと。
そう言ってしまうほど、確かに彼女は小さな怪我をよくする。
鍛練の傷や戦場での傷は多少仕方ないと思えるが、それ以外にも、町を歩いていて(もちろん何もないところで)転んだり、薬草を摘みに行ってうっかり指を切ったりなどなど……周囲の人間はハラハラし通しなのだ。
幼子を見守るような愛情や、純粋な友情。憧憬を含むものから情動を含む恋心まで――想いの方向は人それぞれに違えど、共通して根底にあるのは、神子への愛情だ。
彼女に笑ってほしい。傷ついて欲しくない。
言葉には出さずとも、そんな願いを常に抱えている八葉たちなのである。
それなのに、自らが傷つくことを何事でも無いように言われ、じわりと苦いものが九郎の胸裏にこみ上げる。
「そうか」
軽く頷いた彼は――とても珍しい事に――衝動のまま少女の傷口へと唇を落とした。
「そうですよ――…って、ギャッ! 何するんですか、九郎さん!」
遅れて上がったのは小さな、だが可愛らしさとはかけ離れた悲鳴。
「舐めておけば治るといったのはお前だろう」
身を屈め、望美の指先へ不意打ちのように舌を這わせた男は、さらりと言い放つ。
「だからって、ヒノエくんみたいなことしないでください!」
「なんだそれは」
「いわゆるセクハラ」
「せく…腹…?」
望美の世界の単語であろう謎の言葉に九郎は首を傾げる。だが、傾げていても答えは出ないし、どうせ望美は解説する気も無いだろう。だからあっさりと考える事を放棄する。
「よく分からないが、とりあえず多分あまり良い表現ではないのだろうな」
ヒノエ本人が聞いたら「なんで俺だからよくないことなんだよ!」と反論するであろう科白を吐きつつ、九郎は望美の手を握り直した。
手首を掴んでいた仕草から、手と手を繋ぐ仕草へと。
「あの、くろーさん……?」
普段の九郎からは想像できない行動が続くので、望美は困惑げに彼を見上げた。
常日頃、望美は九郎を振り回している。それはもう景気よく、ブンブンと音がするのではないかというほどに。
その立場が逆転していることに、彼女は戸惑っていた。
手を繋いだ事が皆無とは言わない。戦場では、互いを見失わないために、手と手をとって走る事もある。それとは違う、必要にかられてではない行動に、望美の混乱は頂点に達した。
どこか幼い口調で彼の名を呼び、何故? という問いかけを雄弁に視線に乗せてくる。
しかし彼女の問いかけに答えるべき言葉は、九郎の心の中でも、未だもやもやとしてはっきりしていなかった。
(何故、あんなことをした?)
その衝動へ、明確な名前をつけてしまったら、何か恐ろしいことが起きるような気がする。
だから――とりあえず九郎は適当にごまかすことに決めた。
「よし、戻って弁慶に治療してもらうか!」
誤魔化しで選ぶのがよりによってその言葉か! と、思わないでもないが、望美の意識を逸らす効果は覿面だった。
「ええー! なんで、一体そうなるんですかーっ!」
「弁慶に見つかって文句を言われつつ治療されるより、自己申告して優しく手当てしろってねだる方が、絶対安全だぞ」
望美の抗議の声を無視し、九郎は手をひいて邸へと歩き始めた。
ぶーぶー文句を言いつつも、提言を真面目に考え始めた望美は、捉えられた手はそのままに九郎の後を追う。小走りに追いつき、並んで歩く姿に安堵を覚えた九郎は、無意識に指先へ力を込める。
一瞬の後、同じ強さで握り返される手の温かさ。
――これが、幸せというものなのだろう。
そんな他愛もないことを考えながら、仲間の待つ場所へと歩いて行くのだった。
- END -
||| あとがき |||
この二人の場合、喧嘩友達みたいな関係から、じわじわと互いを意識して、なんとなく…みたいなのに憧れます。
「お前のどこに惚れたのかまったくもってわからなくて、実に不可解なんだが、お前が好きらしい」的ノリで告白するのを想像すると萌えるのですが(※好きという前に惚れたと言ってるあたりがおバカ九郎)、しょっぱなからそれだと甘さもへったくれもないので、もう少し甘い雰囲気に(将来的に)なることを想定して…。
ちなみになんか弁慶が黒っぽい感じですが、弁慶さん好きですよ! 一番最初にクリアしたのは弁慶さんでした。
というか、実はやり始めるまで九郎あんまり好きじゃなかったんだよな…。おかしい、本当におかしい。プレイしている間にじわじわと好きになってました。そして、十六夜EDで一気にメロメロになりました。