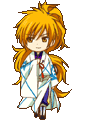拍手御礼再掲
拍手御礼SS 005 … 2010.01.08~2010.01.31まで公開
- ココロ ノ オト
九郎×望美<2章@京>
「馬に乗ってみたいんですよねぇ」
昼下がりの京邸。庭の花々を眺めながらの歓談時に、ぽつりと望美はそんなことを呟いた。彼女の話し相手は、庭で休日を満喫する軍奉行の青年。無論、満喫しているのは彼の趣味である洗濯だ。
「遠乗りがしたいってことかい? うーん、もう少し早く言ってくれたら連れて行ったんだけど、今からだと何処に行くにしても陽が落ちてしまうだろうなぁ」
景時が首を傾げるのに、望美はかぶりを振る。
「そうじゃなくって、自分で馬に乗れるようになりたいんですよ」
「えっ、そーいう意味なの?」
腕一杯に布を抱えて振り返った景時は、視界に映った少女の表情に己も頬を引き締めた。軽い口調な割に、彼女の表情はきつく何かを見据えていて、ただ単に『興味があるから』と告げられた言葉ではないことを景時に知らしめていた。だから景時も、いつも通りの口調で核心をつく問いを投げかける。
「それってさ、もしかして馬に乗れた方が行軍で役立つから?」
「究極にまで突き詰めれば、そんな感じです」
肯定の言葉を紡ぎつつ、望美は両手を頭上で組んでぐっと伸びをした。そのまま背後に倒れ、寝転がるようにして空を見上げる。真っ青な空と白い雲の対比が、九郎の纏う衣のようだなぁ、などと思いながら、望美は景時へ問いかけた。
「どこかに乗馬教室みたいなのってないですよね」
「教室? 教える場所っていうことなら軍の教練所があるけど、流石に望美ちゃんをそこに混ぜるわけにはいかないなぁ」
平家の怨霊を封印する『源氏の神子』として名が知れつつある望美ではあるが、それ以上に彼女の名を軍に知らしめているのは、源九郎義経の許婚であるという一事だ。そんな噂の渦中にある少女を荒武者たちが揃う場所へ連れて行ったら、と思うだけで景時は頭が痛くなる。
「ですよねー」
棒読みで応じる少女に罪悪感を覚えかけた所へ、ある意味救世主となる人物が現れた。
「景時、邪魔しているぞ」
長い髪を微風に揺らしながら歩み寄ってきたのは、源氏の御曹司。
「ん? あぁ九郎か、いらっしゃ~い」
「九郎さん! こんにちはっ」
「望美もここにいたのか」
ぱっと起き上がって微笑む少女に視線を向けた九郎は、その笑みにつられるように笑い返す。その優しげな表情を見た途端、景時の脳裡に天啓がひらめいた。
「あっ、そうだよ望美ちゃん」
「なんですか?」
抱え込んだ洗濯物を、運ぶための大籠に丁寧にしまいながら、景時は目線で九郎を示してみせた。
「乗馬、九郎に教わりなよ」
「えっ!」
「はっ?」
同時に上がった驚きの声を無視して、景時は名案を言ったとばかりに満面の笑みを返した。
数日後。馬を引いて現れた九郎を京邸で出迎えたのは、童水干を身に纏った望美だった。
「……随分と珍しい格好をしているな」
長い沈黙の後に紡がれた言葉に、望美は腕組みをしながら応じる。
「朔が、いつもの服だと足元が危ないからやめなさいって」
「確かにそうだな。鞍には金具とかが沢山ついているし、剥き出しにしていると怪我をしかねな――」
「九郎。朔殿が言いたいのは、そういうことではないと思いますよ」
重々しく頷く九郎の言葉を遮ったのは、彼と共にやってきた弁慶だ。
「そうなのか?」
「分からない九郎がおかしいんですよ。――あぁ望美さん、その衣装もとてもよくお似合いですよ。さ。これは、僕から君への贈り物です」
憐れむような視線を九郎に向けた後、弁慶は望美の手にそっと何かを乗せた。ついでにやんわりと手を包むように握りしめるのは流石熊野男と言ったところだが、受け取る側の方の無関心さ故にあっさりと空回りする。
「なんですか、これ」
「傷薬ですよ。落馬して怪我したときに必要になると思いますから、持って行ってください」
「私が馬から落ちるのは、既に決定事項なんですか?」
「おや、落ちないとでも?」
軽く目を見開いて聞き返す言葉に、望美は黙って視線を反らした。悔しいが、落ちない自信などあるわけない。
望美の仕草で全てを察し、弁慶はさらに笑みを深めた。
「君の愛らしい顔に傷が付かないことを心から祈っていますよ。では練習、頑張ってきてくださいね」
「――ははは、ありがとうございます……」
弁慶の言動と薬湯の味はともかく、傷薬は本当によく効くのだ。有難く利用させてもらうことにしよう、と望美は落とさないように懐奥深くへ傷薬の包みを仕舞い込んだ。
一言二言挨拶を残し、邸の奥へ向かった弁慶を見送りながら、九郎は改めて望美に声をかける。
「準備が出来たら出かけるぞ」
「出掛けるって、京邸でやるんじゃないんですか?」
「弁慶の言葉ではないが、落馬したらここでは痛いだろう。大原あたりまで行けば人も少ないし、草原のようなものだからお前も馬も怪我をしにくいだろうと思うんだが」
どうだ? と問いかける九郎へ、望美は笑顔で頷く。先に歩き出した九郎の後を追って小走りに追いかける望美の歩調にあわせ、ほんの僅かに九郎が歩みを緩める。自然と並んだ相手を見上げ、望美は楽しげに告げた。
「大原へ行くの久しぶりです。楽しみ!」
「おい、遊びに行くのではないのだぞ」
「分かってますってば。――あ、でも歩いていくの?」
「まさか。そんなことしていたら日が暮れてしまうだろう」
門番に預けていた馬の鼻面を軽く叩いてあやした九郎は、ひらりと鞍に跨ると馬上から望美へ手を差し伸べる。
「ほら、掴まれ」
「え?」
「お前が一人で馬に乗れるわけ無いだろう? 大原まで乗せて行ってやる」
なんでもないことのように言われるが、どうしても望美は『二人乗り』ということを意識してしまう。多分、行軍の時だったら気にもしないのだろう。他の仲間もいない、二人きりでの外出で――という状況が、望美に照れを与えていた。
「望美?」
訝しげに名を呼ばれ、再度促すように手を差し伸べられる。
「あっ、はい! 宜しくお願いします」
恐る恐る右手を九郎の左手へ重ねると、骨ばった指が力強く握り返してくる。更に左腕の肘あたりを掴まれ、無造作に――だがその実は、細心の注意を払って鞍上へと引き上げられる。一気に高くなった視界にくらりと惑い、望美は反射的に握られた手に力を込めた。指先の微かな震えに気付いた九郎は、望美の腰を支え、姿勢を整えてやりながら問いかける。
「大丈夫か」
その心配げな声に、望美は数度瞬いてから頷き返した。
「ちょっとびっくりしたけど、もう平気です。……やっぱり馬って、視線高くなりますね」
「怖いか?」
気遣うというよりは、どこかからかうような響きを含んだ問いかけに、望美の反発心がむくむくと起き上がる。
「そんなことないですっ」
「よし、その意気だ」
破顔一笑。門番が寄越した手綱を握りなおし、九郎は愛馬の腹を蹴って合図を送る。
ゆっくりと歩き出した馬上で、九郎の背筋は常以上にぴんと伸びて前方を見据えている。手綱を握る彼の腕に抱きこまれるような形で鞍の前輪に横向きに座った望美は、近すぎる九郎との距離に思わず胸が高鳴ってしまう。どくんどくんと響く鼓動が、密着している九郎に聞こえたら嫌だなと思い、じりじり身体を離そうとするが、成功する前に九郎の腕が望美を戒めた。
「こら、動くな。いくら俺が押さえていても落ちるぞ」
「うっ……すみません」
逆により一層抱き寄せられてしまい、望美は身体を縮こまらせて俯いた。眼下にあるつむじを見下ろし、九郎は小さく溜息をつく。
「望美。緊張するのも分かるが、そういったものは馬に敏感に伝わってしまうぞ。落ち着いて、深く息を吸って――馬の動きに、身体を委ねてみろ。高いのが気になるなら、目を閉じてもいいぞ」
「え? 目を、ですか?」
「ああ。周囲が見えなくなれば、高さを感じる事もなくなるのではないか?」
「でも……」
不安げに見上げた望美へ、九郎は莞爾と笑ってみせた。
「大丈夫だ。お前を落としたりは絶対しない。俺を信じろ」
断言してみせる彼の言葉に促され、望美はきゅっと目を閉じてから、大きく深呼吸をした。
視界が闇に閉ざされると、様々な音が耳へ溢れてくる。馬の蹄が土を蹴る音に、時折ぶるりと鼻を鳴らす暖かな呼吸音。風が木々の枝を揺らす音に混ざって届く人々のざわめき。どれもが意味のある音としてではなく、あるがままの自然な音色として望美の身体を静かに揺さぶっていく。
「どうだ?」
「うん、この方が怖くないみたい」
柔らかく届く九郎の声に甘えるように、望美は僅かに身体を傾けた。その頬がさらりとした布に触れる。
(これは、九郎さんの音だ)
胴鎧越しに聞こえる心臓の音は小さいけれど、静かに刻まれる鼓動にあわせる様にゆっくりと呼吸を繰り返していたら、段々と望美の身体から無駄な力が抜け始めた。
触れる腕に伝わる感触で望美の緊張が解けてきた事を感じた九郎は、安堵と同時に、不意に周囲の様子が気になり始めた。
(なんだか、妙に視線を感じるな)
何気ない素振りで周囲を窺うが、向けられているのは、敵意や隔意といった負の感情ではない。
九郎の大将という地位は伊達ではない。己に向けられる悪意に気付く事が出来なければ、ここまで生き残る事など叶わなかったのだから。その勘が今まで働かなかったということは、少なくとも敵による視線ではない、ということだ。
なんだろう、と九郎は首を傾げる。望美が目を閉じていて見ていないからこそ出来る仕草だが、その僅かに傾いた視線の先で、何故か黄色い悲鳴が上がった。そこには数名の若い娘が顔を寄せるようにして集まっている。
「ほら、やっぱり源氏の若様よ!」
「あの髪型からそうだとはおもったのだけれど……!」
意識が向いてしまったことではっきりと聞きとってしまった言葉の数々に、思わず九郎は手綱を取り落としそうになる。
(なっ、なんだ……!?)
改めて周囲へ気を配れば、そのような類の囁きは、先程の娘たちだけではなく、他の――行商に歩く男女や、それを買い求めようとする女たちなど、其処彼処から漏れ聞こえてくるではないか。
「あら、一緒にいるのは、噂の許婚という姫君かしら」
「でも童の衣装を纏っておいでよ」
「それはきっと姫君が目立たないように、童の衣を着せておいでなのよ」
再び届く少女たちの歓声に、ひくりと馬の耳が震える。
「若様に寄り添うようにして……まるで絵巻物のようで、羨ましいこと!」
そんな笑いさざめく声に茫然する九郎の耳に、今度は男衆の声が届く。
「おお、あれが源氏の神子姫か」
「怨霊を封印する姫というが、なんとも細く小さなお嬢さんなのだなぁ」
だが、そんな感嘆の声に混じって微かに聞こえたのは、どこか野卑た響きを孕む声。
「……御大将の腕の中で目を閉じて震えている様は、中々に興のあるものよ」
「玉の肌が隠されているのが残念だが、童水干姿もまた、なんともいえぬ色香が……」
聞こえてきた会話に、九郎は思わず奥歯を噛みしめる。
『足元が危ないからやめなさいって』
『分からない九郎がおかしいんですよ』
(そういう事かッ!)
色艶を伴う視線が望美に向けられるなど想像したこともなかった九郎は、今更ながらに弁慶が言っていた意味を悟り、口に出せない痛みを胸奥に閉じ込めた。
「九郎さん、ちょっと痛いんですけど……」
戸惑いがちに訴える望美の声で、九郎はふっと我に帰る。いつの間にか、望美が落ちないようにと抱きかかえる腕に力が篭り過ぎていたらしい。
「すっ、すまん」
慌てて謝るが、腕を緩める事はせず、逆にしっかりと彼女の腰を掴む。
「――望美、少し速度を上げるぞ。しっかり掴まっていろ」
「え、九郎さん!?」
宣言すると同時に軽く馬の腹を蹴り、馬に指示を送る。無言の合図に応じて、ぽくぽくと歩んでいた馬が滑らかにに速度をあげていく。有事でもない今は全力で走るわけにいかないが、町中でもこれくらいの速さであればは許される。衆目を振り切り、一気に馬は町の外へと駆け抜ける。
速度が変わった瞬間、一度だけ望美の肩が震えたのが分かったが、九郎の言いつけを守ってか――それとも彼に寄せる信頼が故か、目を開ける事は無かった。だが、振り落とされまいとしてか、九郎の着物の胸元を握り締める指の力が可愛らしく見えて、九郎は彼女に気付かれないようにこっそりと笑った。
「望美、慣れてきたと思ったら、目をあけても構わんぞ」
「はぁい。でも目を閉じてるのも楽しいから、もう少しこのままでいいですか?」
「楽しい?」
鸚鵡返しに問う言葉に、望美は楽しげに首肯する。
「いろんな音が聞こえるんですよ。普段聞こえないような音。まぁ今は、馬の蹄の音と風の音が強いけど――でも、まだよく聞こえるから」
「……俺にはそれ以外、なにも聞こえないが」
「ふふふ、いいんですよ。私だけ、聞こえていれば」
そう告げてぴたりと口を閉ざした望美を見下ろし、九郎は諦めたように息を吐く。
「まぁいい。好きにしろ」
「はーい、好きにしま~す」
声を立てて笑う望美に釣られるように、前方へ視線を戻した九郎の口元にも緩く笑みが浮かぶ。戦も政とも無縁な、気安い言葉のやり取りは、何気ない内容でも九郎の心を穏やかに落ち着かせてくれる。加えて、着物越しに伝わる体温が、九郎の胸中に暖かなものを降り積もらせていくのだ。
「ね、九郎さん」
「なんだ」
「私が馬に乗れるようになった後も、時々こうやって九郎さんの馬に乗せてくれますか?」
「別に構わないが……お前、独りで馬に乗りたかったんじゃないのか?」
「そうですよ。でも、九郎さんと一緒に乗るのは別です」
さらりと紡がれた言葉に、とくん、と九郎の心臓が高い音を刻む。触れる頬でそれを知り、望美はゆるりと頭上へ首を巡らせた。大きく開いた瞳で九郎を視界一杯に捉えた後、彼に気付かれない内に慌てて目を伏せる。
閉じた瞼に刻まれたのは九郎の横顔。その精悍な頬は、かつて見たこと無いほどに紅色に染まっていた。
その記憶を味わうように、望美は短い馬上の旅を九郎の鼓動へ耳を傾けながら過ごしたのだった。
||| 拍手掲載時のあとがき |||
memoでコッソリ書いたシチュエーション募集でリクエスト頂いたお話です。
ええと、少しリク内容と違っちゃいました…orz
頂いたのは「二人で馬に乗って市に現るってどうでしょうか?デート的な!もちろん一匹の馬にふたりのりで」でした。二人乗りは満たしたけど、デートじゃないし、これ! しかも何故かうっかり2章くらいのイメージで書いてしまったので微妙に糖度不足…というか、お互いに意識してるけど、という感じでラブラブじゃないし。
…すみません、こんなんでお楽しみいただけましたでしょうか?(汗)
とにもかくにも、拍手送信ありがとうございました。そして最後までお読みいただきましてありがとうございましたっ♪
- EXTRA - ... 拍手コメントレスに書いた短文焼き直し
「昔、九郎さんに乗馬を教わっておいてよかったなぁ」
モンゴルの草原で、馬に轡を取りつけながら望美は呟く。
「ん? 何故だ?」
その隣で、さりげなく望美の作業を手伝いながら、九郎は首をかしげる。
「だって馬に乗れれば、どこまでも九郎さんを追いかけていけるじゃないですか」
望美の返事に、九郎はふわりと目を細めた。そのまま上体を傾け、望美の目尻に口づける。
突然の事に目を丸くする望美へ、九郎は彼らを包む込む青空のように晴れやかな笑顔を浮かべた。
「馬鹿だな。俺の背を追うんじゃなくて、隣を走ってくれるんだろう?」
「……そうでしたね。勿論、一生ずっと離れませんから」
「ああ、分かってるさ」
二人の声は、僅かな照れと、そして互いへの思いに満ち溢れながら、静かな草原に溶けて行った。